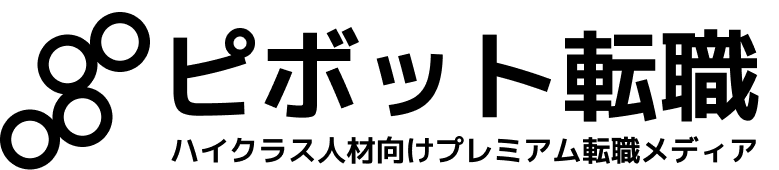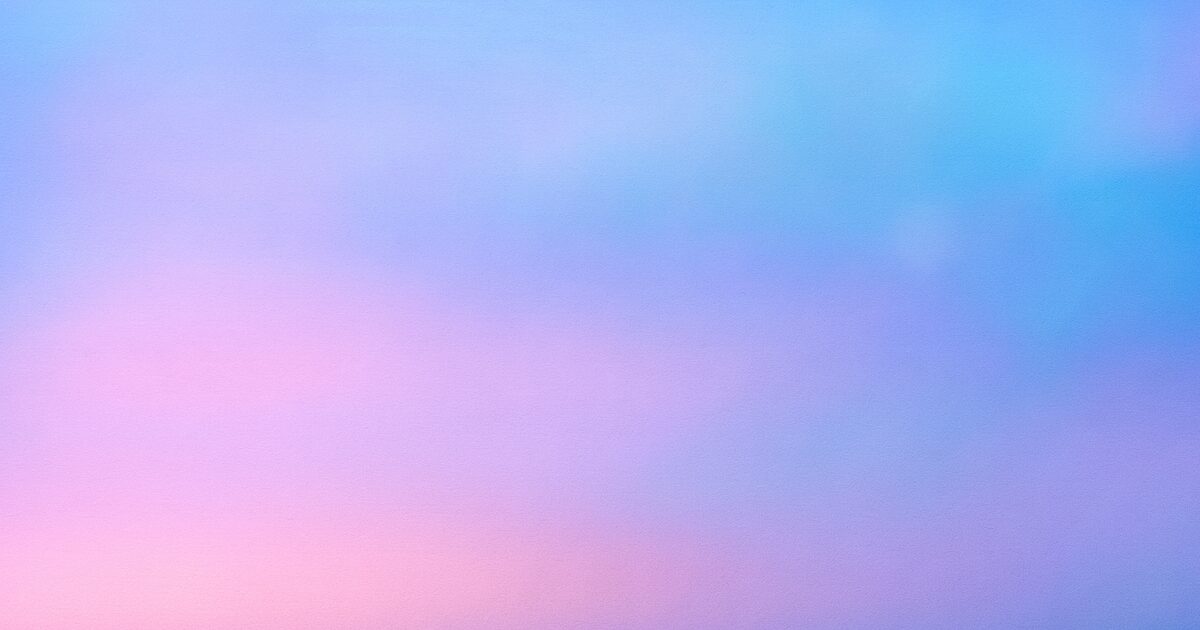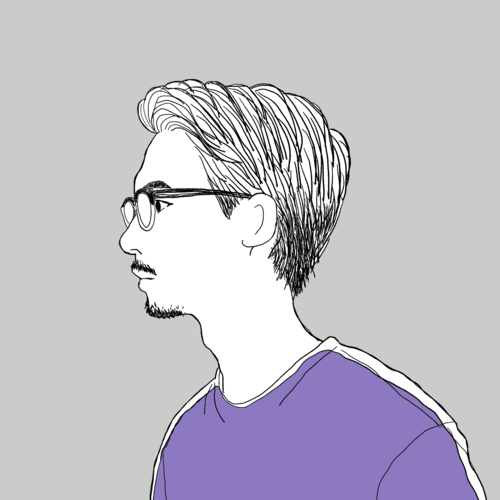30代後半・転職市場の冷徹な現実
「社内政治、根回し……。頭では分かっている。それが組織を潤滑に回すための『必要経費』だということは」
朝霧との会話を反芻しながら、自分は心の中で独りごちた。
だが、自分の答えはNOだ。
理由は明白だ。それらは一歩会社の外に出れば、一銭の価値にもならないからだ。
職務経歴書のスキル欄に『常務への根回しが得意です』『他部署との調整をやっていました』と書いて、一体どこの誰が評価するというのか。
面接官は鼻で笑うだけだろう。
市場が求めているのは、どの会社に行っても通用する、再現性のある『ハードスキル』だ。
時間を使うなら、自分という人的資本に「資産」として残る能力に投資したい。
会社という看板が外れた時、最後に残るのは裸のスキルだけだ。ビジネスパーソンとしての本質は、どこまで行っても「個の力」であるはずだ。
自分は再び、転職サイトのタブを開いた。
組織に媚びるスキルではなく、実力そのものが資産として評価される場所へ。
しかし、意気揚々と漕ぎ出した転職市場という大海原は、想像以上に冷徹だった。
最初に狙ったPE(プライベート・エクイティ)ファンドは、門前払いだった。
「率直に申し上げますと、書類通過率は2割以下です」
エージェントの声は淡々としていた。
投資の実務経験なし、戦略コンサルの在籍期間も短い。「未経験のポテンシャル」だけで通用するほど、資本の最前線は甘くなかった。
提示されたのは、年収が半減するFAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)での下積み。自分は乾いた笑いで断るしかなかった。
ならばと目を向けた中堅企業のCxO職も、壁は厚かった。
ようやく届いたオファーは『経営企画部長候補』。
年収は現在よりダウン。しかも求められるのは、泥臭い社内調整と、オーナー社長への忠誠心。
これなら、今の会社にいるのと変わらない。
スタートアップの求人も見た。
だが、そこに並ぶ「CxO」の文字の実態は、プレッシャーに塗れたB2Bの営業責任者だ。今の自分には守るべき家族がいる。
ストックオプションという名の宝くじを握りしめ、週末も深夜もなく数字に追われる生活に身を投じる覚悟は、今の自分には持てなかった。
季節が二つほど変わろうとしていた。
自分の受信トレイには、丁寧だが冷淡な定型文のメールばかりが積み重なっている。
『誠に残念ながら、今回はご縁がなかったということで……』
まただ。
数ヶ月に及ぶ転職活動の成果が、この淡白なメール一通だ。
PEはスキル不足。
中堅企業は条件不一致。
スタートアップはリスク過多。
気がつけば、あれほど輝いて見えた「市場価値」という言葉が、色褪せた呪いのように自分を縛り付けていた。
「椅子がないなら作るしかない」――起業という論理的帰結
自分は行き場のない溜息とともに、逃げるようにPCを閉じた。
(……他人の作った椅子に座ろうとするから、買い叩かれるんだ)
ふと、そんな思考が脳裏をよぎる。
椅子取りゲームに参加するから、確率論に殺される。ならば、自分で椅子を作ればいいのではないか?
起業。
自分のスキルを最も高く評価してくれるのは、自分自身だ。
戦略立案も、事業計画も書ける。論理(ロジック)こそが最大の武器だ。自分が解決できる顧客ニーズをみつけて解決できれば、あんな理不尽な評価に晒されることもない。
そうだ。葛城(かつらぎ)に会いに行こう。
かつてコンサル時代の同期で、2年前に独立してAI系スタートアップを立ち上げた男だ。
ファームでは「神童」と呼ばれ、最年少マネージャー確実と言われていた彼なら、この閉塞感を打破するヒントを持っているはずだ。
元戦略コンサル(MBB)が起業で陥る「ロジックの敗北」
「正解」のないテスト
指定された場所は、渋谷の雑居ビルにあるシェアオフィスの一角だった。
ガラス張りの小さな会議室に現れた葛城は、自分の記憶にある「切れ味鋭いエリート」とは、何かが違っていた。
「……久しぶりだな、鳴海」
ヨレたTシャツに、無精髭。
目は笑っているが、奥底に澱(おり)のような疲れが見える。
「悪かったな、急に。……実は、起業を考えていて。お前の話を聞きたかったんだ」
自分がそう切り出すと、葛城は苦笑いしながら、手元の缶コーヒーを開けた。
「起業、か。……鳴海、お前は優秀だ。MBB(トップティア)の作法も身についている。だがな、悪いことは言わない。今のままならやめておけ」
「なぜだ? ロジックも組めるし、事業計画も――」
「その『ロジック』が邪魔をするんだよ」
葛城は自嘲気味に言った。
なぜ「優秀なコンサルタント」はスタートアップで失敗するのか?
「俺もそうだった。市場調査も競合分析も完璧にして、勝てるロジック(Winning Formula)を描いた。投資家向けのピッチデックも完璧だった。シードで数千万、サクッと集まったよ。ここまでは『コンサルのゲーム』だったからな」
彼は視線を宙に彷徨わせた。
「でもな、プロダクトを出したら、誰も使わなかった」
「……え?」
「想定した顧客ニーズなんて、机上の空論だったんだ。『ユーザーは合理的じゃない』なんて教科書には書いてあったが、現実はもっとカオスだ。俺たちが得意な『戦略』なんて、戦場では紙屑同然だった」
葛城は指を折りながら、MBB出身者が陥る「地獄」を語り始めた。
「まず、期待値のギャップに殺される。周りは『元戦略コンサルなら成功して当たり前』と思ってるし、自分でもそう思ってる。でも、実績が出ない。『あれ、俺ってこんなに使えない人間だったっけ?』って、毎晩自己否定のループだ」
彼の言葉は、自分の胸に冷や水を浴びせるようだった。
「それに、チームが作れない。俺はエンジニアに対して『なんでこんな論理的な仕様が理解できないんだ』って詰めちまった。結果、創業メンバーは半年で辞めた。『あなたは正しいけど、ついていけない』って言われてな」
「……お前ほどの人間に?」
「ああ。投資家からは『論理は分かった。で、君自身は何ができるの?』と聞かれる。コードも書けない、泥臭いテレアポもプライドが邪魔してできない。俺たちにあるのは『正解を探す能力』だけだ。でもスタートアップに正解なんてない」
資金ショートとアイデンティティの崩壊
葛城はスマホを取り出し、画面をタップした。そこにはSNSの画面があった。
「見てみろ。元同期の連中は、ファンドでパートナーになったり、大企業の役員になったりしてる。あいつらの人生は『第3章、第4章』と進んでるのに、俺だけまだ『第1章』の泥沼でもがいてる。成功ストーリーの中に、自分の居場所がない焦燥感……これが一番キツい」
そして彼は、声を潜めて付け加えた。
「先週、妻に言われたよ。『いつまで夢を見てるの? 保育園代、来月から上がるのよ』ってな。……コンサル時代の貯金も、会社のバーンレート(資金燃焼率)であっという間に溶けた。来月の資金繰りを考えると、吐き気がする」
戻るのも怖い。進むのも怖い。
エリートとしてのプライドと、現実の無力感の板挟み。
「鳴海。ここは『ロジック』で攻略できるゲームじゃない。論理という武器を捨てて、泥水をすする覚悟がある奴だけが生き残れる。……お前に、その覚悟はあるか?」
葛城の問いかけに、自分は即答できなかった。
彼が纏っているのは、かつての「憧れの先輩」のオーラではなく、戦場で傷つき、血を流し続けている兵士のそれだった。
「……効率が悪いな」
思わず口をついて出た言葉に、葛城は寂しげに笑った。
「ああ。最高に非効率で、非合理的だ。だからこそ、まだ誰もやっていない価値がある……とは思うがね」
行き止まりの交差点で、その名は灯る
シェアオフィスを出ると、渋谷の街は夕暮れに染まっていた。
人混みの中で、自分は立ち尽くした。
社内政治の泥臭さから逃げ、転職市場の冷徹さから逃げ、そして今、起業という選択肢さえも「ロジックの通じない荒野」であることを知らされた。
会社に残れば、飼い殺し。
外に出れば、漂流。
自分で作ろうとすれば、遭難。
いっそ、戻るか。
思考の振り子が、大きく逆側へと振れる。
かつて自分がいた、外資系戦略コンサルの世界へ。
確かに、短期間で転職を繰り返す「ジョブホッパー」のレッテルを貼られるリスクはある。
一度離れた人間に冷たいファームもあるだろう。
何より、そこは完全実力主義の「Up or Out(昇進するか、去るか)」の世界だ。常に競争に晒され、気の休まる時間などない。
だが、そこには明確な「ルール」があった。
曖昧な社内政治や、理不尽な感情論ではない。
明確なスキル項目と、提供したバリューによって昇進が決まる、ドライだが公正な世界。
今の会社のような生ぬるい地獄より、ヒリつくような戦場の方が、よほど精神衛生上マシなんじゃないか?
(……結局、自分にはそこしか居場所がないのかもしれない)
そうやって自分を納得させようとした、その時だった。
ポケットの中でスマホが震えた。
画面に表示された名前を見て、自分は息を呑んだ。
『朝霧 透』
あの喫茶店での別れ際以来の、連絡だった。
(→ 第6節|「黄金の手錠」と「社内政治」という名の仕事 へつづく)