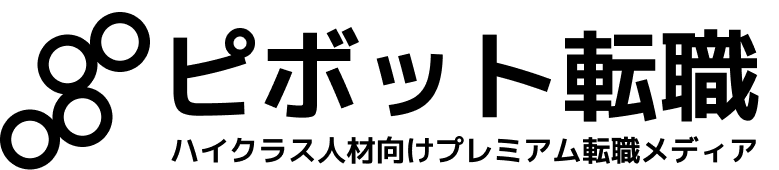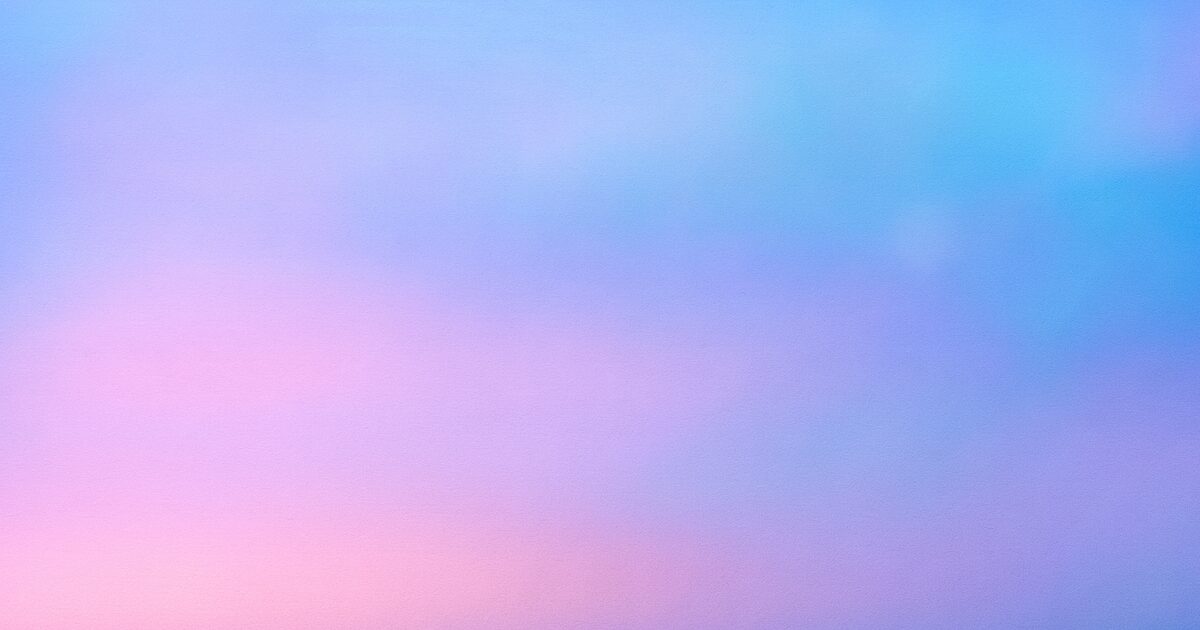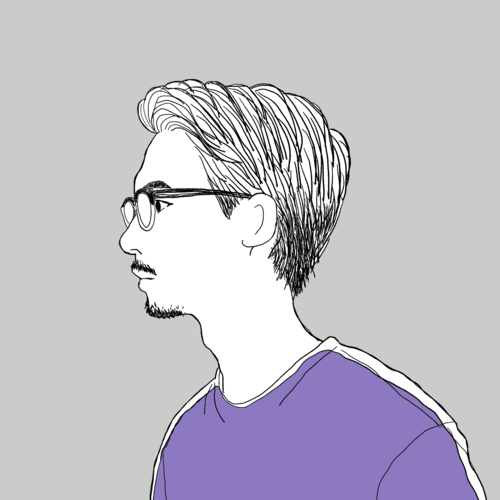敗者の安息地と、予言された結末
「……なら、戻ればいいじゃないか」
自分の迷いを見透かしたように、朝霧は言った。
場所はいつもの喫茶店『YOhaku』だ。だが、窓の外はすでに漆黒の闇に包まれている。
昼間の穏やかな空気とは異なり、夜の店内には重厚なジャズが低く流れ、アンティークのランプが鈍い光を落としていた。
朝霧はカウンターの奥で、コーヒーカップではなく、琥珀色の液体が入ったロックグラスを傾けていた。その横顔は、周囲の喧騒から切り離されたように静謐だった。
「遅かったな」
「……急な呼び出しでしたから」
隣の椅子――昼間よりも革の匂いが濃く感じられるスツール――に腰を下ろしながら、自分は短く答えた。
朝霧は私の方を見ることなく、氷が触れ合う音を楽しみながら口を開いた。
「顔を見れば分かる。……全滅だったようだな」
心臓が早鐘を打った。
なぜ、この男には全てお見通しなのか。
PEファンドでの門前払い、中堅企業での失望、そして葛城から突きつけられたスタートアップの現実。ここ数ヶ月、自分が味わってきた屈辱の旅路が、彼の前では全て透明なガラスケースの中の出来事のようだった。
「転職エージェントは、君の『地頭』は褒めたが『実績』がないと切り捨てた。スタートアップの友人は、君の『ロジック』は正しいが『熱量』がないと否定した。違うか?」
「……盗聴でもしていたんですか」
「推測だ。君のような『優秀な迷子』が辿るルートは、大抵決まっているからな」
朝霧はそこで初めて私の方を向き、悪戯な子供のような笑みを浮かべた。
「そして今、君はこう考えている。『いっそ、古巣のコンサルに戻ろうか』と。……思考停止の極みだな」
図星だった。
カッとなって言い返そうとしたが、言葉が出てこない。
「……正直、そう考えていますよ。起業のようなギャンブルより、確実なリターンが見込める。それに、今さらマネージャーに戻るつもりはない。ディレクターや、あるいはPEのシニアポジションなら、もっと裁量を持って経営にインパクトが出せるはずだ」
自分は努めて冷静に言った。
年収は3,000万、あるいは5,000万を超える世界。そこに戻れば、「負け犬」の烙印は消える。
しかし、朝霧は憐れむような目でこちらを見て、短く笑った。
「裁量? 確実なリターン? ……鳴海君、君は何も見えていないな」
彼は懐からスマートフォンを取り出し、画面をタップして私に見せた。
そこには、業界紙のニュースが並んでいた。『〇〇ファンド、パートナー交代』『大手コンサル、売上目標未達で再編』。
「君が戻ろうとしているのは、『論理の楽園』じゃない。『政治と営業の伏魔殿』だ」
コンサルティングファームの真実:「選挙」に勝てるか?
「いいか、シニアマネージャーまでは『デリバリー(実務)』の能力で評価される。だが、プリンシパルからパートナーへの壁は、全く別の競技だ」
朝霧は指を一本立てた。
「必要なのは『論理的思考力』じゃない。『集票能力』だ」
「集票……ですか?」
「パートナーになるということは、ファームの共同所有者(株主)になることだ。既存のパートナーからすれば、自分たちの利益(パイ)を分け与える相手を選ぶ行為だ。そこで問われるのは、『こいつは優秀か?』じゃない。『こいつは俺の財布を潤すのか?』だ」
朝霧の言葉が、かつての上司たちの疲れた顔と重なる。
「年間数億円の売上ノルマ(Sales)は、単なる足切りラインに過ぎない。本当の勝負は『スポンサー(推薦人)』集めだ。有力なパートナーに『こいつは俺の派閥の人間だ』と認めてもらい、昇進委員会(コミッティ)という名の密室で、反対派を論破してもらう。そのための根回し、貸し借り、社内接待……。君が嫌悪している『社内政治』の、最も高度で陰湿なバージョンがそこにある」
「……実力だけじゃ、上がれないというんですか」
「実力があっても、政治力がなければ潰される。あるいは、他のパートナーと担当業界(テリトリー)が被れば、『俺の客を奪う気か』と拒否権を発動される。それが『Up or Out』の正体だ。君は、昼はクライアントの機嫌を取り、夜は社内の有力者の機嫌を取る『選挙活動』に、残りの人生を捧げたいか?」
さらに、朝霧は実務的な「詰み」についても指摘した。
「それに今のファームは慢性的な人材不足だ。自分が取ってきた案件を任せられるマネージャーがいない。優秀なジュニアは次々に転職していき、残ったメンバーは疲弊している」
「案件を回すために自分が現場に入り込めば、営業に割く時間は消える。営業に集中すれば、デリバリー品質が落ち、炎上案件の火消しに呼び戻される。どちらを選んでも、どこかが破綻する。このジレンマに挟まれたまま、『アップ・オア・アウト』の最終コーナーに突入していくのがオチだ」
PE・VCの真実:「黄金の手錠」と「見えない鎖」
私は言葉に詰まった。だが、まだ反論の余地を探していた。
「なら、PEファンドはどうです? 投資家として、資本の論理で……」
「もっと悪い」
朝霧は即答した。
「PEのシニア層が抱えるのは、『案件枯渇』と『汚れ役』のストレスだ。今の市場、まともなオークション案件は高すぎて買えない。独自ルートでの相対(アイタイ)案件を探し回りながら、投資期間(インベストメント・ピリオド)のタイムリミットだけが、じりじりと近づいてくる」
「ここで打席に立たなければ、何も残らない。でも、この高値で入れば、将来の減損リスクは高い――そう分かっていながら、どこかでバットを振らざるを得ない。その一振りが失敗したとき、傷つくのは投資先企業だけではない。君自身のキャリアそのものだ」
さらに彼は、投資実行後の現実を突きつける。
「投資後も楽にはならない。送り込んだ経営陣が機能せず、PMI(統合プロセス)は空回り。不人気なリストラやコストカットを現場に押し込み、自分は憎まれ役を買う。『経営を良くするため』と分かっていても、数百人の従業員の人生に、自分の決裁一つでメスを入れる――その感覚に、夜眠れなくなるシニアは少なくない」
「……VC(ベンチャーキャピタル)なら、もっと夢があるはずじゃ」
「VCのパートナーこそ、『ホームラン』の呪縛に囚われている」
朝霧は氷を揺らした。
「10社のうち1社がユニコーンにならなければ、他がそこそこ良くても『負け』だ。結果、どうなると思う? 本質的な支援よりも、Twitter(X)でインフルエンサーごっこをして知名度を上げ、若手の天才起業家に『選んでもらう』ための広報活動に時間を費やすことになる」
「本当は、粛々と投資先の事業や数字と向き合っていたい。にもかかわらず、タイムライン用の一言コメントに悩む時間のほうが増えていく……。君は、承認欲求モンスターのような若造のご機嫌取りをするために、キャリアを積み上げてきたのか?」
人生のROI(投資対効果)の崩壊
「それに、一番の問題は『出口(Exit)』がないことだ」
朝霧の声のトーンが落ちた。
「シニアクラスになれば、年収は3,000万、5,000万と跳ね上がる。生活水準も上がる。子供はインターナショナルスクール、住まいは港区のタワーマンション。一度その生活レベル(バーンレート)を上げると、もう下げられない。これを業界用語で『ゴールデン・ハンドカフス(黄金の手錠)』と呼ぶ」
私の胸に、鋭い痛みが走った。
まさに今の自分が、その予備軍だったからだ。
「PEなら『キャリー(成功報酬)』という人質も取られる。今の仕事が嫌でも、『あと3年我慢すれば数億円入るかもしれない』という期待が、君を今の椅子に縛り付ける。だが、その3年後にファンドが失敗したら? ……君は50歳手前で、市場価値のない、プライドだけが高い『元エリート』として放り出される」
朝霧はグラスに残った液体を飲み干し、私を真っ直ぐに見据えた。
「組織の中で『偉くなる』ということは、自由になることじゃない。『より高給で、より責任が重く、より代わりの効かない奴隷』になることだ。君が求めていた『個の力で生きる』というゴールから、むしろ遠ざかっているとは思わないか?」
反論できなかった。
コンサル、PE、VC。
エリートたちが目指す山の頂(いただき)は、下から見れば輝いて見えた。だが、実際にそこにいる者たちは、酸素の薄い場所で、滑落の恐怖と戦いながら、終わりのない「政治」と「数字」のゲームを続けている。
自分はその山を登りたかったのか?
いや、違う。
私が欲しかったのは、誰かの評価に怯えることのない、確かな「手触り感」のある成功だったはずだ。
「……八方塞がりですね」
私が力なく呟いた。
「塞がっているのは、『雇われて偉くなる』という道だけだ」
朝霧はゆっくりと首を横に振った。
「君が嫌がっている社内政治も、PL責任も、人のマネジメントも、結局どこへ行ってもついて回る。だが、それを『他人の財布』のためにやるか、『自分の城』のためにやるか。その違いは天と地ほどある」
彼は、一枚の名刺をカウンターに置いた。
「椅子取りゲームに参加するな、と前にも言ったはずだ。椅子を作る才能がないことも、君は認めた。ならば、残る選択肢は一つしかない」
朝霧の目が、夜闇の中で鋭く光った。
「――椅子を『買う』んだ」
(→ 第7節|「王道」という名の裏口入学 へつづく)