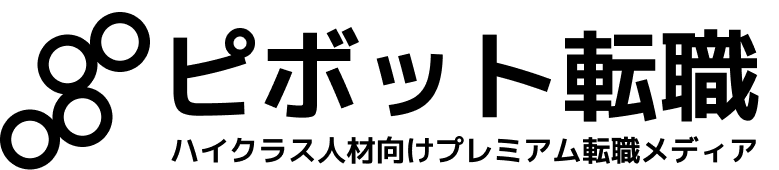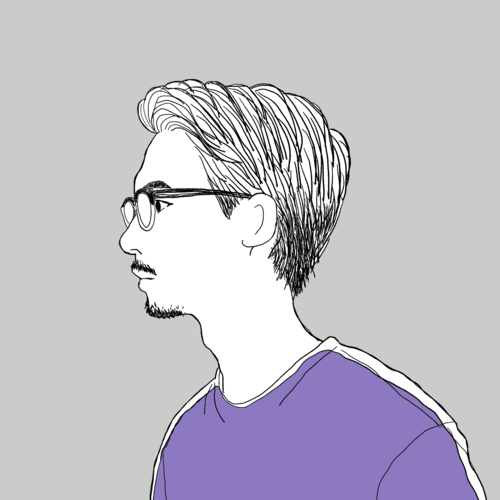1. 正しさは「壁」であり、曖昧さは「扉」である
神楽坂、『YOHaku』。
店内の古時計が、ボーン、ボーンと低い音を立てた。
「戦略的……曖昧さ?」
鳴海は眉間の皺を深めたまま、その言葉を反芻した。
「曖昧なんて、ビジネスでは悪です。定義が揺らげば、KPIもぶれるし、責任の所在も不明確になる。磯崎の企画はまさにそれだ。あれは戦略じゃない、ただの手抜きです」
白洲は穏やかに微笑んだまま、カウンターの奥から一冊の古びた本を取り出した。
「鳴海さん。君の企画書は、この本のようなものだ」
それは、文字がびっしりと詰まった、分厚い哲学書だった。
「完璧で、隙がなく、著者の主張が論理的に完結している。読者はただ黙って、それを『勉強』させられるだけだ。君のロジックは鋭利すぎる。それは武器だ。武器を持って近づいてくる人間に対し、組織という生き物は本能的に防御する。それが『拒絶』だ」
次に白洲は、スケッチブックのようなノートを広げた。そこには、ラフな線画と、いくつかの単語だけが書かれている。
「一方、磯崎さんの企画はこれだ。これを『統一可能な多様性(Unified Diversity)』と呼ぶ」
「統一可能な……多様性?」
「そう。『最高の顧客体験』や『未来を描く』といった抽象的な言葉は、誰からも反対されない。営業は売上のことだと思い、開発は技術のことだと思う。定義を曖昧にすることで、対立する部署同士を一つの旗の下に集めることができるんだ」
白洲は赤鉛筆の先を、その余白部分にトントンと当てた。
「人はね、他人の完璧な論理に従うのは苦痛なんだよ。でも、自分の解釈を挟む余地があるものには、愛着を持つ。磯崎さんの企画はスカスカだからこそ、役員たちはそこに『自分の手柄になる可能性』を見出したんだ」
鳴海はハッとした。
権藤本部長の言葉が蘇る。『俺たちが口を出す隙間がなかった』。
「つまり……俺は完璧な地図を描くことで、彼らから『口を出す楽しみ』を奪ったということですか?」
「それだけじゃない。君は使い分けを間違えたんだ」
白洲は指を二本立てた。
「『Why(なぜやるか)』は曖昧に。多くの人を巻き込むためにね。
『How(どうやるか)』は明確に。現場を混乱させないために。
君は『Why』までガチガチに定義して、相手の退路を断った。それが敗因だ」
正しさは、人を排除する壁になる。
曖昧さは、人を招き入れる扉になる。
鳴海は冷めてしまった珈琲を、一気に飲み干した。苦味が喉を通り過ぎていく。
「……俺は、ずっと一人で戦っていました。バカな上司を論破することが、仕事だと思っていた」
「論破して勝てるのは、ディベートの大会だけだ。組織で勝ちたいなら、敵を論破するのではなく、敵を『共犯者』に仕立て上げなきゃいけない」
白洲はそう言うと、いつものように古い赤鉛筆を耳に挟んだ。
2. 未完成の地図への書き換え
翌日。東京駅のオフィス。
プロジェクト・ネクサスのキックオフミーティングが終わった直後だった。
磯崎が、自席で頭を抱えていた。
「やべえ……権藤さんに『夢があっていい!』って褒められたのはいいけど、具体的な実行プラン、全然詰められてないわ。オペレーションどうすんだこれ……」
いつもの鳴海なら、鼻で笑って無視していただろう。『Why』だけで勝負した人間の末路だ。
だが、昨夜の白洲の言葉が、呪いのように頭に残っていた。
——『Why』は曖昧に、『How』は明確に。
鳴海は、ARグラスの通知をオフにした。
そして、自分のデスクの引き出しから、昨日却下された「完璧な企画書」を取り出した。
(これを、そのまま渡しては意味がない)
彼はその資料を複製し、修正を加え始めた。
まず、断定的な表現を削ぎ落とす。「Aルートを使用すべき」という結論を削除し、「複数のルートオプションにより、状況に応じた柔軟な対応が可能」と書き換える。これは「リスクヘッジ」のための曖昧さだ。
次に、プロジェクトの最終目標(Why)に関する記述をすべて削除し、空白にする。
残したのは、膨大なシミュレーションに裏打ちされた「地下インフラの稼働データ」や「ドローンの飛行可能空域」といった、客観的な事実(How)の積み上げだけだ。
結論を消し、問いに変える。
完璧な青写真を、あえて「他人が入り込む余地のある地図」へと劣化させる作業。
その作業には、身を切るような痛みがあった。自分の作品を汚すような行為だ。しかし、鳴海はそれを手に、磯崎の席へと歩み寄った。
「磯崎」
「うわ、鳴海……。昨日は悪かったな、その、ドンマイっていうか」
磯崎が気まずそうに目を逸らす。
「お前の『未来マルシェ構想』だが、面白い視点だと思ったよ」
心にもないお世辞を言った。胸の奥でプライドが軋む音がする。
「ただ、具現化するには裏付けがいるだろ。僕が昨日ボツになった資料の中に、使えそうなデータがあるんだ。……ただの素材だが」
鳴海は、あえて「結論」を抜いたデータ集を渡した。
そこには、「こうすべきだ」という主張は書かれていない。ただ、「このエリアにはこれだけのポテンシャルがある」という事実の断片だけが並んでいる。
磯崎は警戒しながらそれを受け取り、パラパラとめくった。
「え、これ……すげえな。地下インフラのデータ、こんなに詳細にあるのか? これを使えば、俺のマルシェ構想、配送コストをゼロにできるんじゃ……」
磯崎の目が輝き始めた。
「そうか! 鳴海、ここ! この空きスペースを使えば、お前が言ってたドローンも飛ばせるんじゃないか? そうすりゃ、俺のやりたい『温かみのある配送』と、お前の『効率化』、両立できるぞ!」
鳴海は、口の端が少しだけ上がるのを止められなかった。
それは、鳴海が昨日のプレゼンで主張し、却下された結論そのものだったからだ。
しかし、今、そのアイデアを思いついたのは鳴海ではない。
磯崎だ。
磯崎が、鳴海の用意した曖昧な余白の中に、答えを「自分で発見した」のだ。
「……いいアイデアだな、磯崎。それなら、権藤さんも納得するんじゃないか」
「だよな! うわー、天才か俺。サンキュ鳴海! お前、意外といいやつだな!」
磯崎は興奮して、すぐに権藤への報告メールを打ち始めた。
3. 黒子の勝利
数日後。
プロジェクト・ネクサスの修正案が、役員会で正式承認された。
その内容は、磯崎の「ビジョン(Why)」を皮切りに、中身は鳴海が設計した「ロジック(How)」で埋め尽くされたものだった。
「いやあ、磯崎君の柔軟な発想には驚かされたよ。地下インフラとドローンを、あんな風に『街の風景』として溶け込ませるとはね」
権藤本部長は上機嫌だった。
自分の可愛がっている磯崎が手柄を立て、しかもその内容は、役員たちが懸念していた収益性もクリアしていたからだ。
会議室の隅で、田島が小声で鳴海に囁いた。
「鳴海さん……あれ、実質的には鳴海さんの元の案そのものですよね? 名前は磯崎さんになってますけど、いいんですか?」
鳴海は、プロジェクターに映し出された資料を眺めた。
作成者名は「磯崎」。自分の名前はない。
以前の自分なら、屈辱で腸が煮えくり返っていただろう。
だが、不思議と不快感はなかった。
自分の描いたロジック(How)が、磯崎という「曖昧なインターフェース(Why)」を通すことで、組織という巨大な生き物を動かし、現実の社会実装に向かって動き出したのだ。
自分の名前が載ることよりも、「自分の書いたコードが正しく動作した」ことへの静かな満足感があった。
「いいんだ、田島」
鳴海はARグラスに表示された『プロジェクト承認』の文字を見つめた。
「誰が手柄を取ったかよりも、誰がその絵を描いたか。……それを知っている人間がいれば、それでいい」
それは強がりでもあり、新しい「生存戦略」への第一歩でもあった。
正論という剣を振り回すのをやめ、曖昧さという霧の中に身を隠し、組織をコントロールする。
これもまた、一つのゲームの攻略法かもしれない。
鳴海はふと、神楽坂の地下にあるあの店を思った。
白洲は言っていた。
『自分の物語を取り戻せ』と。
会社の物語の中で「主役(リーダー)」になろうとして、自分を見失っていた昨日まで。
だが、会社の物語を「利用」して、自分の仕事を成し遂げる黒子(編集者)のような立ち位置。
それは、ほんの少しだけ、会社という虚構から自由になった感覚だった。
「さて、仕事に戻るか」
鳴海は踵を返した。
その足取りは、昨日よりもわずかに軽かった。