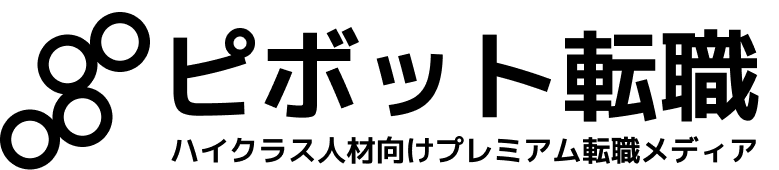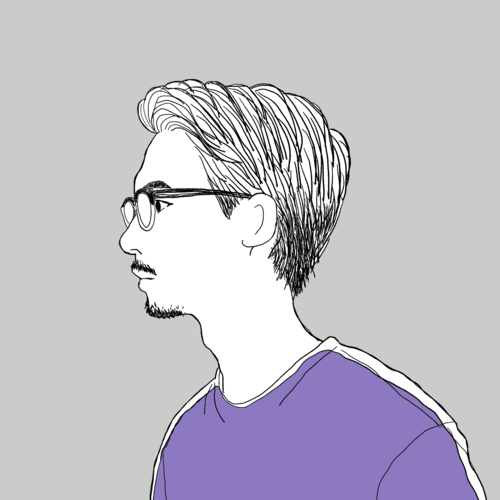私はこれまでGAFAや外資系戦略コンサルティングファーム、スタートアップのユニコーン企業とキャリアを歩まさせていただきました。
その中で、書籍や雑誌で名前を見るようなマーケティング業界や経営界のトップクラスの方とも仕事をさせていただいたことは、私にとってはかけがえのない財産です。
そんな、業界トップクラスの人がおすすめしてくれた書籍の中から、私がオススメする本をこの記事で厳選してご紹介します。
仕事をする全ての人がマーケティングを理解すべき理由
本の紹介の前に、「働く全ての人」と私が書いた背景を解説します。
「私はマーケティングに関わる仕事をしていないから」とマーケティングを理解しないのは本当に損をしているからです。
現代経営学の父、ピーター・ドラッカー氏も企業に必要な機能は「マーケティング機能」「イノベーション機能」「経営管理的機能」の3つのみだといいます。ちなみに、「イノベーション機能」は「マーケティング機能」と一括りにされることもあるので、いかにマーケティングが重要な話かおわかりいただけるかと思います。
ちなみに、ピーター・ドラッカーは有名経営者のファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井正氏も影響を受けた人物なので、これ以上私がすごさを力説せずとも重要さを理解いただけるかと思います。
まさに、マーケティングを知らないということは、世の中の構造や仕事について知らずに働くようなのものなのです。
マーケティング入門書ならこの6冊【常識】
前置きが長くなってしまいましたが、それでは早速マーケティングの本を紹介していきましょう。
最初は、「マーケティング理論に慣れるための本」としてとっつきやすい本のご紹介です。
基本的に、マーケティングは学問として発達しており、熟読すべきは学者の方・専門家が書いた内容の厚い本です。それだけで足ります。
ただ、いきなりその本に飛びついて、面白さがわからないとハードルをあげてしまうため、実務家が書いた難易度の低い本を、ご紹介していきます。
たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング
P&G、ロート製薬 執行役員マーケティング本部長、ロクシタンジャポン代表取締役、SmartNewsマーケティング担当執行役員を歴任された西口 一希氏による著作。
エグジット経験のある先輩から、スタートアップで雇いたいマーケターといえばこういう人だよね、と紹介してもらったのが、西口 一希氏とその書籍でした。
内容としては、「セグメント」や「消費者定量調査・定性インタビュー」といったマーケティング実務を行う方が日常的に実施する内容が、西口氏の経験された事例とともに綴られており、理解しやすい一冊。
USJをV字回復させた森岡毅の実戦マーケティング3部作【3冊 合本版】
P&G、P&G米国本社、USJのCMO・マーケティング本部長を歴任された森岡 毅氏の著作。
最近は、メディアへの露出も増やしており、ビジネスパーソンの間でも認知が広がっている方です。
本書は、「USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?」「USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門」「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」3冊の合本版となっており少々高いのですが、私はこちらを書いました。
処女作の「USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?」は、初めての著書ということもあり、物語調でマーケティングの理論的な内容は若干薄い感じもします。ただ、新しいアイデアを生み出すためのツールなど他の書籍にはない内容もあり、目を通して損はありません。
「USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門」では、マーケティングフレームワークの森岡 毅氏の考え学ぶことができます。
「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」では、市場構造を決定づける要因についてわかりやすく解説されています。仕事において注力すべきポイントがわかる良書です。
ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム
「イノベーションのジレンマ」で日本でも一躍有名になった、クレイトン・M・クリステンセンの著作。イノベーションのジレンマに続き、こちらも世界中で大ヒット。クレイトンの人気ビジネス書作者としての地位を不動のものにした本と言えるでしょう。
クレイトン自身はマーケティングの実務家ではないため、マネージメント関連書籍として紹介されることが多いですが、この本は商品・サービス開発の本質をシンプルに理解でき、まさにマーケティングの入り口に最適の本です。
「マーケティング」といえばこの書籍6冊【厳選】
続いて、マーケティング本の定番中の定番をご紹介していきます。多くがP&Gで活躍していた先輩に紹介していただいた本です。有名実力はマーケターもこういった本を読んで勉強したんだ、と思うと自分にも自信がつきます。
売れるもマーケ 当たるもマーケ―マーケティング22の法則
著者のアル・ライズは実務家のマーケターからも一目置かれるマーケティング関連本の著者として有名です。
市場がどのように形成され、その市場で「行った方がいいこと・行ってはいけないこと」が22の法則としてわかりやすくまとまっています。
マーケティングの面白さをここまでわかりやすく、そして楽しく教えてくれる著者はアル・ライズいないでしょう。
ポジショニング戦略 [新版]
同じくアル・ライズの著作。「ポジショニング」という言葉を耳したことがないビジネスパーソンはいないと思いますが、その原型を作った本がこちらの本です。
中身は少なめなので、サラッと何か読みたいときに読むのがおすすめです。
マーケティング脳 vs マネジメント脳 なぜ現場と経営層では話がかみ合わないのか?
この記事でのアル・ライズの著作紹介はこちらでいったん終了です。
この本は「マネジメント脳がなぜ失敗するのか?」をわかりやすく教えてくれます。
マネジメント脳とは何か?
戦略コンサルティングファームで働くコンサルタントの方をイメージしていただくといいでしょう。頭脳明晰、ロジカルに答えを導き出す専門家です。
ただ、この「スマートな人たち」が事業会社の経営につくと、うまく行かないケースが多い。その理由がわかる本です。
私はちょうど有名戦略コンサルティングファームの元コンサルタントと仕事をしているときにこの本を読んでいたのですが、その優秀な元コンサルタントの方はまさに「ロジカルに正しく、マーケティング的に間違った方向へ」いくんですよね。そんな現場をみて改めてマーケティングを学ぶことの大切さを実感しました。
コトラーのマーケティング4.0 スマートフォン時代の究極法則
マーケティングといえばこの人、フィリップ・コトラー氏、の著作です。スタンダートとして、色々なところで一部の内容が転載されていますが、やはり本質は本人の言葉で綴られた本書でしか深く理解できませんね。
Marketing 5.0: Technology for Humanity
フィリップ・コトラーの「マーケティング4.0」のシリーズ次の著作です。
2021年1月に発売され、本記事執筆時点ではまだ翻訳されていないようですが、早めに読んでいただくのがおすすめです。
内容は、テック企業が得意としてきたプロダクトグロースやマーケティングテクノロジーが加わり、マーケティングにおけるより細かい分析やコミュニケーションが求められる未来がみえる書籍となっています。
コモディティ化市場のマーケティング論理
フィリップ・コトラーの著作の日本語版のほとんど全てに関わっている恩蔵 直人氏の著作です。恩蔵 直人氏は、早稲田大学商学学術院長、商学部長、早稲田大学常任理事などを歴任されている方です。
コモディティ化市場においてとるべき戦略がわかりやすく整理、解説されています。
コモディティ化、というとスタートアップでイノベーティブなことをやろうとしている方には響きづらいかもしれませんが、コモデティ化はアプリビジネスからYouTubeチャネルまでいたるところで日々起きています。
そんな企業の宿命ともいえる競争とコモデティ化を通じて、マーケティング理論を学ぶことができる書籍で、個人的に一押しの本です。
イノベーションのための思考法を身につけるならこの5冊【注目】
個人的に、21世紀の人材に特に必要になってくる能力がこのイノベーションやクリエイティビティと呼ばれる、新しいことを発想する力だと思っています。
ピーター・ドラッカーのいうところの顧客の創造やマーケティングの商品・サービス開発といった大き目の話から、マーケティングコミュニケーションの独自性創出など、クリエイティブで新しいことを考え出す思考法を身につけるために読むべき本をご紹介します。
イノベーションのDNA[新版] 破壊的イノベータの5つのスキル
スティーブ・ジョブズやジェフ・べゾフ、イーロン・マスクのような稀有な起業家がどのように物事を捉え、アイディアを出し、そして事業化をしているか、その思考方法がわかる名著。
こちらも、「ジョブ理論」同様「イノベーションのジレンマ」の著者、クレイトン・M・クリステンセンの著作です。
原作の「The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovator」は2011年7月に発売されていたのですが、日本ではようやく2021年10月18日翻訳版が発売予定のようです。英語が苦手な方は、こういった知るべき知識を10年遅れでようやく読めるようになったりするのですから本当不利ですよね。
発想法 [改版] 創造性開発のために
発想法の元祖、川喜田 二郎氏の発想法全2巻の1巻目。ユーザーインサイトを元に商品・サービス開発を行うプロセスそのもに適用できる方法を学ぶことができます。
最近流行りのデザインシンキングが元としている本質を深く学ぶことができる名著。実験室で行う実験科学との対比で、いかに実地で行うユーザーインタビューや調査(野外科学)が大事かも明快に整理、解説されている。
この本は、原型がなんと「1976年」に書かれています。書籍の中では、日本人とアメリカ人の発想における能力の違いなどもあり、改めて欧米の方の真似だけをせずに日本人の強みを活かすことの大切さも学ぶことができます。
続・発想法 KJ法の展開と応用
川喜田 二郎氏の発想法全2巻の2巻目。本書は、1巻目から時間を経て、著者が必要と感じたアップデートを発送法にかける書籍。
この発想法が日本の大企業で使われくらいに広まるようになると、コンサルティングファームからも研修の依頼がきていたとのこと。その研修を受けたのが私がお世話になったファームかはわからないが、確かに外資系戦略コンサルティングファームでも、インタビューという野外調査を非常に大事にしてアウトプットにつなげている。
アイデアのつくり方
著者ジェームス W.ヤング氏が、広告代理店勤務自体にクリエイティブな施策アイディアをいかに発想していたかをまとめた本。
この本は非常に薄く、その薄さと内容ゆえにAmazonのレビューも1と5が交互に並んでいる。私がこの本を、思考法を身につけるための本に書いたのはこれが実は理由で、他のクリエイティブな発想に関する本を読んだ後に読むと、なぜ5をつける人がたくさんいるのか理解していただけると思う。
アナロジー思考
アナロジーという強力な発想法を深く学べる本。
「アナロジーとは借りる力」であると本書では定義しており、特定の業界や通念に縛られずに全く違う分野から発想を得る方法が学ぶことばできる。
有名アニメ作家から起業家まで、現在の多くのクリエイティビティはさまざまなものの組み合わせで生まれており、ぜひ読んでおきたい一冊である。
デザインリサーチの教科書
デンマーク・コペンハーゲンのCopenhagen Institute of Interaction Designを卒業している木浦幹雄氏の書籍で、デザインリサーチの入門としてオススメです。
デザインリサーチのトレンドの変化など、全体像を掴むことができる1冊。
「ブランド」を学ぶならまずこの2冊【定番】
ブランド関連の本については選定に迷いました。ブランドの使われ方や文脈が業界などに少しブレがあるからです。
例えば、消費財企業出身者の方にとっては、ブランドとは商品そのものを指すことが多く、その場合、そもそもブランドというものだけを切り取ることはナンセンスということになるでしょう。(真逆に、ブランドは商品の補完である、という方もいます。)
一方、私のようにテック企業出身者にとってみると、プロダクトがある程度うまくいった段階で、消費者が想起するイメージを戦略的にコントロールしていく作業がブランディングであり、「ブランド」を創ろうと意気込んでいる起業家は少数派かと思います。(まさに、商品の補完としてのブランド。正確には、もともとブランド自体はあるが、ブランドという言葉で語られていないともいえますね。)
例えば、Facebook社がある程度大企業になった後に、Instagramのデザインを大きく変えるなど、各ロゴのデザインをこまめに修正し始めたことからも、テック企業がブランディングというものに注力するフェーズのイメージは持っていただけるのではないでしょうか。
最近だと、Robinhood などもIPO前にブランド規定を刷新していたりするので、徐々にテック企業もブランディングに取り組む時期は早くなってきはいますが、まだまだ創業期からブランディングに投資するのは一般的ではありません。
シリコンバレーの著名投資家Hamilton W. Helmerは、ブランディングは会社が安定期に入ってから出ないと、インパクトのある効果を出さないと著書のなかで説明しています。
そこで、この記事では、あなたがこれまで意識していなかった自社サービスのブランドを考えようかな、と思った時にすぐに役立てていただける本を厳選ししました。
ブランディング 7つの原則【改訂版】成長企業の世界標準ノウハウ
世界的なブランドコンサルティングファームである、インターブランドジャパンが編著した書籍です。
インターブランドは1974年にロンドンで設立された世界最大のブランディング専門会社で、様々な企業にブランドコンサルティングを提供している第三社だからこそ書けるブランドの基本全てが抑えられる書籍になっています。
「明日からブランドについて考えなければいけない」そんな時にもすぐに行動に移せる知識をくれる教科書的な本です。
ブランディング 7つの原則【実践編】
同じくインターブランドジャパンが編著した書籍で、ブランディング 7つの原則で学んだことを、実際の企業事例で理解を深めることができる書籍です。
個人的には、一風堂やマツモトキヨシなど慣れ親しんだブランドのブランド戦略は学ぶことが多かったです。
ブランド論―無形の差別化を作る20の基本原則
現代ブランドの父と呼ばれるデービッド・アーカー氏の書籍です。
賛否両論ある書籍で、他の書籍を読んだ後だと物足りない感じはあります。ただ、この本書籍ならではの整理の仕方などもあり、ブランドについて理解を深めるにはとても役立ちます。
プロダクトグロースで有名なこの3冊【必読】
シリコンバレーのテックスタートアップから広まった「グロース」という考え方。近年では、スタートアップ界隈では当たり前のものとして根付き、また消費財メーカや食品メーカー、化粧品メーカといった大企業でもグロースの要素を取り入れる動きが当たり前になってきました。
グロース・マーケティング、といった職種をみる機会もだいぶ増えてきましたね。採用ブランディングの一環として、営業や通常のデジタルマーケティングにグロースと名前がついているだけのケースもあり、転職者は少し注意したいところでもありますが。
Hacking Growth グロースハック完全読本
グロースといえばこの本でしょう。Dropboxでグロースの責任者を担っていたショーン・エリス氏と、Facebookでグロースを担当し現在Shopifyのグロース責任者であるモーガン・ブラウン氏の著作。
2017年に発売された本ということもあり、動きの早いスタートアップの方にとっては昔の本という印象もうけるかもしれませんが、読んだことがない方はまず目を通したいグロースの教科書的な本です。
グロースハック 予算ゼロでビジネスを急成長させるエンジン
Hacking Growthを読んだ後に「日本の事例を読みたい」、そう思った方はこの本がおすすめです。2014年発売で事例は古いのですが、今もスタートアップグロースの基礎に流れる考え方について、事例とともに理解を深めることができます。
Hooked ハマるしかけ 使われつづけるサービスを生み出す[心理学]×[デザイン]の新ルール
Nir Eyal氏による、Amazon.comのインダストリアルデザイン書籍ランキングで1位のベストセラー本です。
グロースで重要な「ユーザーの継続率(リテンションレート)」をいかに上げるか、シンプルなフレームワークで理解することができます。
残念なことに、翻訳の質が悪いようでAmazonのレビューは荒れ気味です。英語に抵抗がない方は原本である「Hooked: How to Build Habit-Forming Products」をオススメします。
Hooked: How to Build Habit-Forming Products
「Hooked ハマるしかけ 使われつづけるサービスを生み出す[心理学]×[デザイン]の新ルール」の原題です。
データマーケティングならまずこの1冊
グロースに続き、スタートアップでの当たり前がマーケティング全体であたり前になりつつある領域の2つ目、データを使ったマーケティングに関する書籍をここで1冊ご紹介しておきます。
データ・ドリブン・マーケティング―最低限知っておくべき15の指標
米国マーケティング協会が選ぶ「2011年のマーケティング本No.1」に選ばれた、ケロッグ経営大学院マーク・ジェフリー氏の書籍。データを主軸としたマーケティングについてアカデミックに整理した書籍で、全体像の把握に役立ちます。
「言うは易く行うは難し」の領域で、インフラが古い大手企業ではまだまだこれから手をつけていかなければいけない領域でしょう。その分、伸び代もある領域だと思います。
顧客リテンションを学ぶために読みたい4冊【最前線】
「サブスクリプション」という言葉がバズワードのごとく流行っている昨今ですが、そんなサブスクと表裏の関係にあるのが顧客のリテンション(継続)になります。
スタートアップにとっては、ユーザーのリテンションさえあれば後は資金調達をしてアクセルを踏み込める、と言われるくらい重要なマイルストーンになっていますね。
また、新規顧客獲得は既存顧客の維持の5倍以上のコストがかかるといわれている中で、大手企業にとっても顧客のロイヤルティ向上は益々大きなテーマになってきているように感じます。
The Membership Economy: Find Your Super Users, Master the Forever Transaction, and Build Recurring Revenue
日本語訳版はないようなので、原本をそのままご紹介します。戦略コンサルタント出身のRobbie Kellman Baxter氏の書籍で、Netflixなどの事例を通じてメンバーシップエコノミーという概念を導入した書籍です。
各論のフレームワークは少々疑問を挟む余地があるのですが、オーナーシップエコノミー vs メンバーシップエコノミーという対立概念の立て付けはぜひ頭に入れておきたい内容です。
売上の8割を占める 優良顧客を逃さない方法―利益を伸ばすリテンションマーケティング入門
元WOWOWコミュニケーションズ取締役営業本部長 大坂 祐希枝氏の、WOWOWにおけるリテンションマーケティングの事例を紹介した本。
もともとマーケティングのバックグランドがなかった大坂 祐希枝が自ら気づいたモデルを惜しげもなく公開してくださっている貴重な一冊。
体型整理や汎用性は学者の書く本に比べて劣りますが、実行した実務家の言葉はパワフルで内容は濃いです。
売上につながる「顧客ロイヤルティ戦略」
顧客ロイヤルティを向上させる方法を様々な事例を通じて学ぶことができる一冊。
スーパーオオゼキの個店主義、ソニー損保のロイヤルティを主要指標とした戦略などぜひ目を通したい事例ばかりです。
お客様の心をつかむ心理ロイヤルティマーケティング 「心の満足」と「頭の満足」を測り、科学的にロイヤルティを高める手法
2017年に出版されたこちらの書籍は、2015年に出版された上記の『売上につながる「顧客ロイヤルティ戦略」』を意識して書かれた印象があり、よりフレームワークを作り込んでいます。
現場でどこまでできるか、という点は気になるところですが、顧客リテンションの考え方をしっかり整理しておく上では非常に有益な書籍です。
口コミ伝染病
人気ビジネス書籍を多数出されているの神田昌典氏の著作です。
セールスライティングの本の著者として有名な神田昌典氏ですが、この本は「口コミ」という既存顧客のリテンションを軸としたビジネスの拡大手段に正体を当てており、この章でしょうかいさせていただきました。
神田昌典氏本は中小企業の事例が盛り沢山で、規模の小さな会社や個人事業でもすぐにできるものばかりです。
マーケティングコミュニケーションを実践するならまずこの3冊【人気】
マーケティング施策を実行する際の外部コミュニケーションの基礎、メッセージ作成について学べるコピーライティング・セールスライティングの本をここではご紹介します。
マーケティングで用いるコンテンツは、動画や静止画など様々なフォーマットがありますが、テキストによるメッセージはまず真っ先にマスターしたいところです。
明確に商品やサービスの情報を伝えられるのはテキスト(言葉)を通じてのみだからです。
また、動画や静止画はデザインセンスも要求され一朝一夕ではマスターが難しいですが、コピーライティングやセールスライティングは今日からでも実践することができます。
ここらで広告コピーの本当の話をします。
博報堂にてコピーライターをされていた小霜 和也氏の著作。長年大手企業のコピーライターをされてきており実績に裏打ちされたコピーライティング本です。
タグラインやキャッチコピーの基礎が学べる良書。
最強のコピーライティングバイブル―伝説の名著3部作が1冊に凝縮! 国内成功100事例付き
米国でコピーライティングの名著と言われる3冊(3部作4冊)を1冊にまとめた意欲作です。
日本の事例も豊富で非常に実践的な書籍です。全体をサラッと一気に読み、実際に自分が実践するたびに見返して身につけていただくのがオススメです。
禁断のセールスコピーライティング
本記事2回目の登場となりますが、神田昌典氏のセールスコピーライティングに関する著作。
様々な機会に同士が発信されている内容のまとめ本のため、体系だっている感じはないのですが、会社の規模にかかわらずすぐに使えるテクニックが学べます。
2014年に書かれた書籍で事例もチラシやDMが多いのですが、今流行りのD2Cなどイーコマース事業運営者も応用できる内容です。ライティングスキルが、時代が変わっても通用するスキルだということを実感します。
心理学・行動経済学をマーケティングに活かすならこの3冊
最近はニューロマーケティングという言葉が出てきていますが、人間の心理的特性・脳の作りをマーケティングに活かそうという動きは益々活発になってきています。
私も注力して勉強している領域で、今後も紹介する本をアップデートしていければと思います。
影響力の正体―説得のカラクリを心理学があばく
心理学の本ですが、マーケティングコミュニケーションに転用できる内容が多々書かれています。
オリジナル版は1984年に発売され、その後アメリカでは改訂版が繰り返し出されているロングセラー人気書籍。
あなたはなぜ値札にダマされるのか?―不合理な意思決定にひそむスウェイの法則
人の心はこうも簡単に操られてしまうのか、ということを様々な実験例を通じて紹介してくれる本です。
企業の餌食にならないために、つい色々買ってしまう消費者の方にもぜひ読んでいただきたい一冊。
予想どおりに不合理 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」
デューク大学 心理学・行動経済学教授のダン・アリエリー氏による著作。
様々な実験結果を通じて人間の「不合理」さを明らかにしていきます。誰もが聞いたことがあるであろうプラシーボ効果の応用事例など、多数の事例と解説があり濃い一冊です。
実践 行動経済学
2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー 氏による著作。ニューヨークタイムズベストセラー本や、フィナンシャル・タイムズとエコノミストのベストブック・オブ・ザ・イヤーなどにも選出され、累計200万部以上売れた有名行動経済学本です。
マーケティング関連本まとめ記事No.1への思い
実は、私は30歳になるまで「マーケティング」をろくに勉強しようとしていませんでした。そして猛烈に後悔しました。数冊の著名な本に触れたとき、マーケティングの威力と大切さを痛感したのです。
そこで、必死で読むべきマーケティングの本を、インターネット上の情報はもちろん、マーケティング企業として有名なP&Gの先輩や、エグジットして成功している知り合いの起業家の方、さらにはアマゾン上にあるマーケ関連本とそのレビュー、他サイトでの評判を片っぱしから調査していきました。
そして、作ったのが私の「マーケティング関連インプット用書籍リスト」です。それを基にこの記事を書きました。
マーケティングの素人からマーケティングの仕事をするようになった私だから書ける、まとめ記事になったのではないかと自負しています。
上記の調査にあたっては当然ながら「マーケティング おすすめ」など関連ワードをGoogleで日本語・英語ともに検索し、それらのウェブサイトを私も目を通していますが。
しかし、残念ながら多くのウェブサイトがアフィリエイトを目的にしているせいか、売れやすい日本人が書いた書籍や大衆向けの書籍の紹介がほとんどでした。
さらに残念ながら、資金のある大手企業によってそういったメディアが運営されていることもあり、質がそこまで高くない書籍を紹介しているウェブサイトが検索結果では上位を独占していたりします。まさに負のループですね。
このピボット転職は、ハイクラスビジネスパーソン向けの最高のメディアになるという使命の元、私が仕事で「役に立った」と思ったもののみをご紹介していきます。
洋書しかみつからないものは、お構いなしに洋書を紹介しています。外資系企業で働いている、あるいは外資系企業への就職を目指している読者の方には特に問題ないと想定してのことです。
まだまだ私の日々新しい書籍を目を通していますので、この記事も進化させられるよう精進していきます。もしその他におすすめの本などあれば、ぜひお問い合わせからご一報ください。
年収2,600万円の過程で私が使った転職サイト
現在このような記事を書いている私ですが、キャリアのスタートは日系中小企業で年収360万円からでした。その中で、自分なりにキャリアアップ・年収アップするために必要な考え方やスキルを身につけていった形です。
そして、私が年収2,600万円にいたる過程で、転職サイト・転職エージェントには非常にお世話になっており、特におすすめの転職サイトを「年収2,600万円の過程で実際に使ったハイクラス転職サイト【厳選まとめ】」という記事にまとめています。
転職を目指してこの記事を読まれた方には、非常に強い味方になるかと思いますので、興味があればチェックしてみてください。(現在のところ、無料で公開しています)
年収2,600万円の過程で私が使った転職サイト
現在このような記事を書いている私ですが、キャリアのスタートは日系中小企業で年収360万円からでした。その中で、自分なりにキャリアアップ・年収アップするために必要な考え方やスキルを身につけていった形です。
そして、私が年収2,600万円にいたる過程で、転職サイト・転職エージェントには非常にお世話になっており、特におすすめの転職サイトを「年収2,600万円の過程で実際に使ったハイクラス転職サイト【厳選まとめ】」という記事にまとめています。
転職を目指してこの記事を読まれた方には、非常に強い味方になるかと思いますので、興味があればチェックしてみてください。(現在のところ、無料で公開しています)