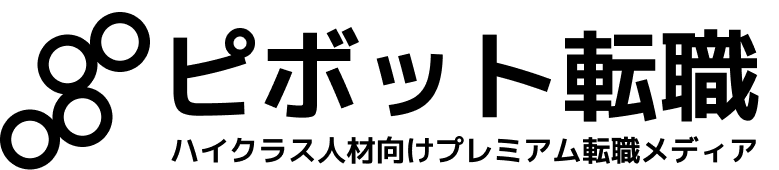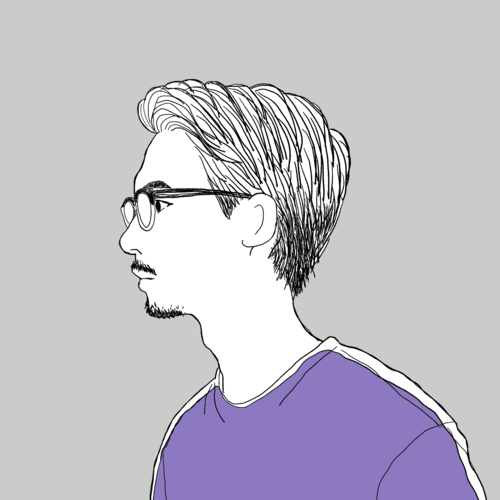プロジェクトの承認フローが、また止まった。
今度のボトルネックは、法務部のマネージャー、高城塔子(48)だ。
社内では「法務の鉄の女」と恐れられている。彼女のデスクの前では、どんなに勢いのある新規事業案も、「コンプライアンス」という名のシュレッダーにかけられる運命にある。
僕は彼女のデスクの前に立っていた。手には、完璧なリーガルチェック済みの契約書案がある。
「高城さん、この条項の修正は弁護士確認済みです。リスクは最小化されています」
高城は分厚い眼鏡の奥から、冷ややかな視線を投げかけた。
「リスクはゼロじゃないわね。それに、このスキームは前例がないわ。もしトラブルが起きたら、誰が責任を取るの?」
「ですから、そのためのリスクヘッジ条項を……」
「時期尚早よ。差し戻します」
書類がデスクに投げ返される。
僕は唇を噛んだ。
論理的には、僕が正しい。彼女はただ、「前例がない」という恐怖心だけで、会社の利益を阻害している。
だが、外から来たばかりの僕には、その壁を突破する術がなかった。
1. 現金払いしかできない男
その時だった。
「お疲れ様ですー! 高城さん、ちょっといいですか?」
能天気な声と共に現れたのは、磯崎だった。
彼は僕のような転職組とは違う、新卒からこの会社一筋の「生え抜き(プロパー)」だ。
彼は僕が突き返されたばかりの案件よりも、さらにリスクが高そうな「地域限定・配送パートナー契約」の書類を持っていた。中身はスカスカで、ツッコミどころ満載だ。
僕は心の中で嘲笑った。
ロジックで武装した僕が通らないのに、そんな落書きが通るはずがない。
「磯崎くん、これ……契約形態が曖昧すぎるわよ」
高城が呆れたように言う。
「いやあ、そうなんすけどね。でも、現場の熱量が高いうちに進めないと、向こうの組合がへそ曲げちゃうんすよ。なんとか、仮承認だけでも!」
磯崎は手を合わせて拝むような仕草をした。
門前払いだ。そう思った瞬間、高城の表情がふっと緩んだ。
「……しょうがないわね。但し書き付きの条件付き承認で通すわ。あとでちゃんと修正しなさいよ」
「うっす! ありがとうございます! 高城さん、マジ女神!」
高城は判子を押し、磯崎に書類を渡した。
僕は唖然とした。
「……待ってください。なぜですか? 書類の完成度は、僕の方が遥かに高かったはずです」
僕の抗議に、高城は眼鏡の位置を直しながら冷たく言った。
「鳴海さんの案件は、不安なのよ。それだけ」
廊下に出た後、僕は磯崎を問い詰めた。
「どういうマジックを使ったんだ? お前の書類はゴミだったぞ」
磯崎は書類をヒラヒラさせながら笑った。
「ああ、中身? 確かに適当だったな。でもさ、俺、新卒で配属されたのが総務だったろ? その時、高城さんが残業してる時に夜食の差し入れしたり、年末の膨大な契約書整理を手伝ったりしたんだよね。もう10年も前の話だけど」
「……10年前?」
「その時の『ツケ(貸し)』が、まだ残ってたってだけだよ。高城さん、義理堅いからさ」
2. 政治的資本(Political Capital)
「それは不公平だ……!」
その夜、神楽坂『YOHaku』のカウンターで、僕はグラスを叩きつけるように置いた。
「仕事の質じゃなく、過去の『貸し借り』で承認が決まるなんて。そんなのはプロの仕事じゃない。ただの村社会の馴れ合いです」
白洲さんは、黙って僕のグラスに新しい氷を入れた。
「鳴海さん。君はスーパーで買い物をする時、何を使う?」
「……現金、あるいはカードですが」
「そうだね。君は今、組織という市場で、**『正論という現金』**だけで買い物をしようとしている。だがね、組織の重い扉を開ける鍵は、現金じゃ買えないんだよ」
白洲さんは、カウンターの下から古びた通帳のような手帳を取り出した。
「組織を動かす力。それを経営学では**『政治的資本(Political Capital)』と呼ぶことがある」
「政治的……資本?」
「簡単に言えば、『信用残高』**だ」
白洲さんは赤鉛筆で、空中に天秤を描く動作をした。
- 貸し(Deposit): 相手が困っている時に助ける。顔を立てる。手柄を譲る。これが貯金になる。
- 借り(Withdrawal): 無理を聞いてもらう。リスクを取らせる。失敗をカバーしてもらう。これは貯金の引き出しだ。
「生え抜きの磯崎さんには、10年以上かけて積み上げた高城さんに対する『定期預金』があった。だから、多少のリスクという『引き出し』が可能だった。
一方、転職してきて日が浅い君の残高はいくらだ?」
僕は言葉に詰まった。
僕はこれまで、他部署の非効率を指摘し、論破し、仕事を奪ってきた。
助けたことなど、一度もない。
「……ゼロ、です。いや、これまでの態度を考えれば、マイナスかもしれません」
「そうだろうね。残高不足の余所者に、銀行はお金を貸さない。君がどれだけ正しい事業計画(ロジック)を持っていっても、審査に通らないのは当然だ」
白洲さんは、優しく諭すように続けた。
「多くの人は『貸し借り』を、汚い裏取引だと思っている。でも違う。
『情けは人のためならず』という言葉は、道徳の話じゃない。投資の話なんだよ。
いつか自分が困った時に引き出すために、日頃から周囲に小さな貸しという種を撒いておく。それが、組織で生きるということだ」
3. 最初の「投資」
翌日の午後。
僕は再び、法務部の高城のデスクに向かった。
手には、昨日の契約書……ではない、別の資料を持っていた。
「高城さん」
彼女は書類から目を離さずに、「修正はできたの?」と面倒そうに言った。
「いえ、今日は僕の案件ではありません。実は、高城さんが今、営業部とのコンプライアンス研修の調整で揉めていると聞きまして」
高城の手が止まった。顔を上げ、怪訝そうな目で僕を見る。
「……なんでそれを?」
「社内チャットのログで見ました。営業部長が『忙しい』を理由に日程を決めないそうですね。
僕、営業部長とは前のコンサル時代からの知り合いなんです。よろしければ、僕から彼にロジックを通して、研修の必要性を説明してきましょうか? 彼が納得するようなデータも作れます」
高城は目を丸くした。
「……あなたに、なんのメリットがあるの? これはあなたの担当業務じゃないわよ」
「ええ。僕の評価には1ミリも関係ありません」
僕は、昨夜の白洲さんの言葉を反芻しながら、不器用に笑ってみせた。
「ですが、会社全体のコンプライアンスリスクを下げるためには、必要なことですから」
高城はしばらく僕の顔をじっと見ていたが、やがてふっと息を吐き、肩の力を抜いた。
「……あの部長、数字にはうるさいから。頼める?」
「お任せください」
僕はデスクを離れた。
背中に、「ありがとう」という小さな声が聞こえた気がした。
手元の手帳には、まだ何も書かれていない。
だが、僕の心の中の通帳には、チャリンという微かな音が響いた。
それは、初めて僕が手に入れた、**『見えない通貨』**の重さだった。