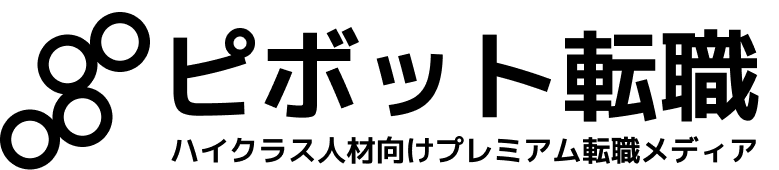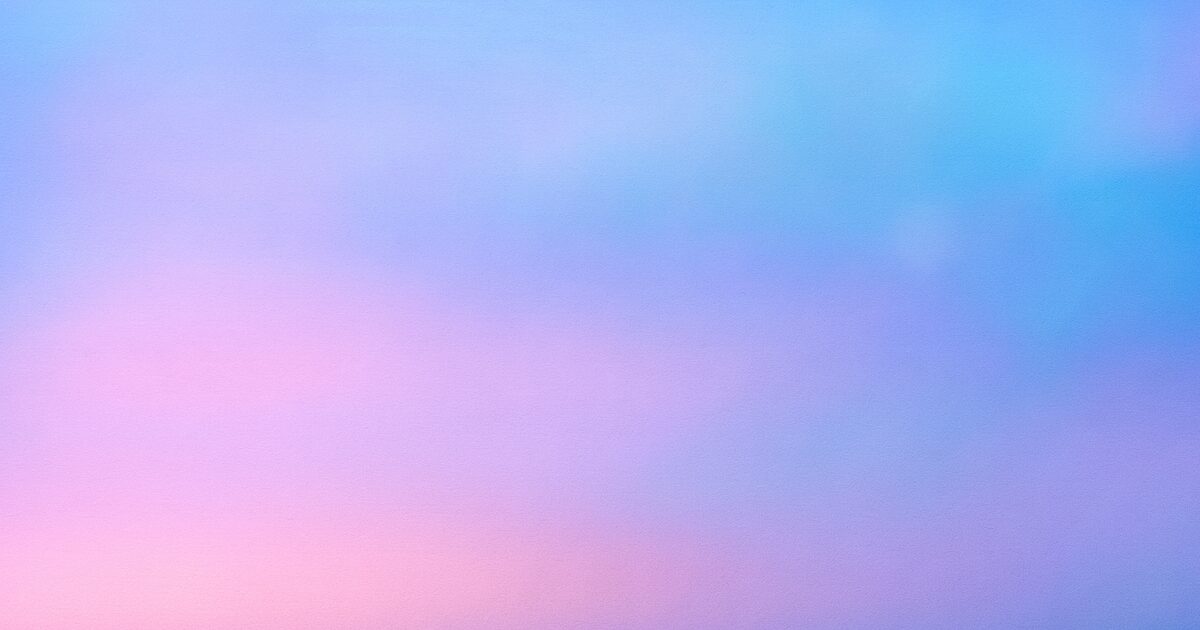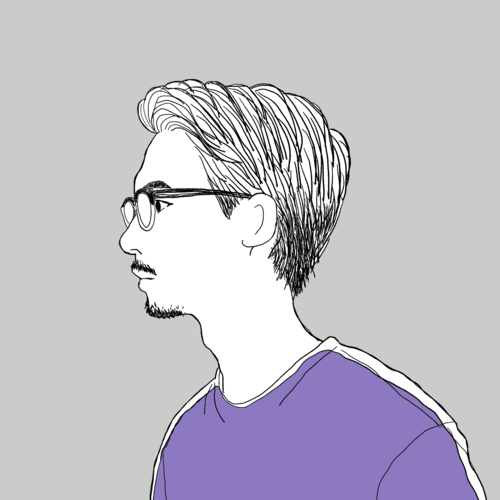東京駅の地下通路は、夕方になると人の波が絶えない。
スーツ姿の人々が忙しなく歩き続ける中で、鳴海一真はその流れに逆らうように、わざと歩幅を小さくして進んでいた。2029年度の人事評価面談を終えたばかりだった。
胸の奥が妙にざわつき、そのざらつきが呼吸のたびに広がっていくような感覚がある。
三十六歳、ジョブレベル5。
会社の制度上は “ミドル層”“次の昇格候補” と説明される階層だが、実態は違う。責任ばかり増えて権限は与えられず、部下も持てない立ち位置に据え置かれている。
プロジェクトを回す力はあると自負しているし、エンジニア陣からの信頼も厚い。
それなのに、組織の構造のどこかで自分だけが“止まっている”ように感じていた。
職歴だけ見れば、もっと評価されてもいいはずなのに。
「オブジェクティブは達成している。君の論点整理力は評価している。
ただね……周囲との“バランス”とか“協調性”の点で、少し懸念が上がっていて」
面談結果は、またしても「平均」。
上司は婉曲に、しかし確かに釘を刺すように言った。
毎年ほとんど同じ文言。具体的に何が悪かったのか聞いても、明確な回答は返ってこない。
“何となく”が評価を決める。
そんな構造が、この会社には確かに存在していた。
評価への違和感は、キャリアの根元を揺らす。
実際、評価は二極化していた。
エンジニアリーダーたちは強く彼を推す。
「判断が速い」「論点が見える」「議論が進む」。
日々のプロジェクトを共にした仲間たちからの言葉だ。
一方で、数回しか接点のない関連部署からは、
「強引」「空気を読まない」。
原因は、あの会議。
議論が堂々巡りしていたため、正しい結論を提示して切り上げた。それが“和を乱した”と受け取られた。
レベル5の給与レンジの上限近くにいるらしく、昇給額は数万円。
インフレ下では実質マイナスで、年収もほぼ頭打ちだ。
“努力すれば報われる”という信念が揺らぐ。
さらに追い打ちをかけるように、尊敬していない同期がジョブレベル6に昇格したと耳にした。
新卒からの生え抜きで、特別なスキルがあるわけでもない。
ただ、無難で、穏やかで、会社にとって“扱いやすいタイプ”。
そんな人物が先に昇格していく現実が、胸の奥に静かな痛みを残した。
「俺は、何を間違えたんだろうか」
妬みなのか、自分の欠点なのか、運なのか。
どれも少しずつ当てはまる気がして、どれかに責任を押し付けることもできない。
考えれば考えるほど、自分の立ち位置が曖昧になっていく。
地上に出ると、東京駅丸の内口の空はすでにオレンジ色から群青へと移り変わりつつあった。
若い頃、この景色を初めて見たときは、
「ここから何者にだってなれる」と素直に思えた。
だが今は、その感覚が遠い。
駅前のコンビニにふらりと入り、何となく缶コーヒーを一本だけ買う。
プルタブを開けると、小さな音が喧騒に吸い込まれていった。
口に含んだ苦味が、今日の面談の記憶と混ざり合い、舌の上に残る。
——俺は今、どこにいる?
胸の奥に沈殿する問い。
電車に向かう足は重く、一真はしばらくホームに立ち尽くした。
人の流れの中に自分の居場所を見つけられぬまま、ただ次の電車を待つ。
(→ 第2節|家の温もりと、現実の重さ へつづく)