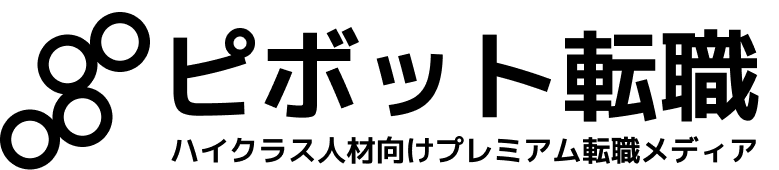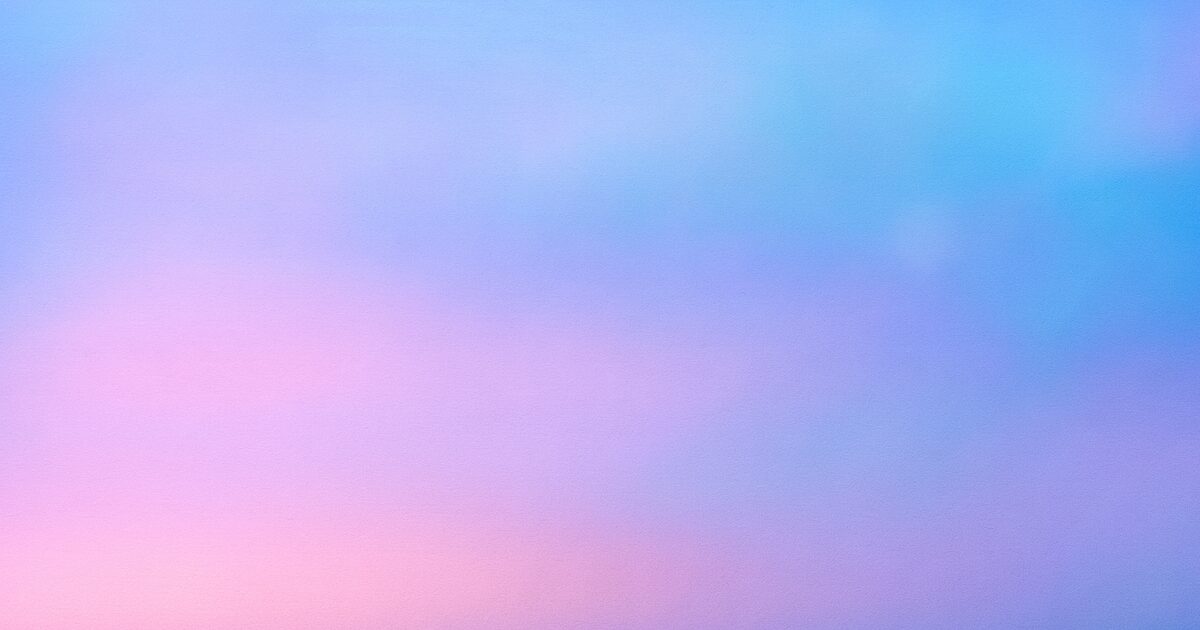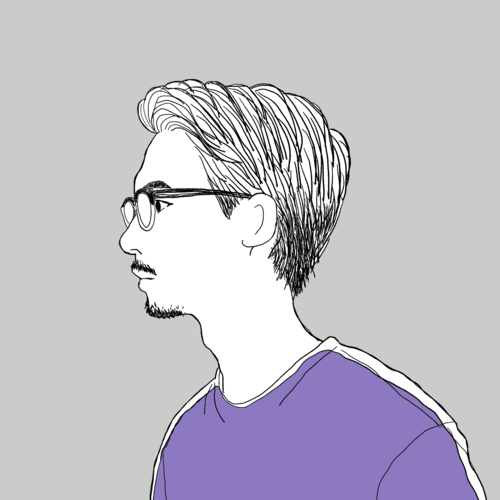神楽坂の静寂と、招かれざる「構造の悪魔」
「……いい場所でしょう」
ふいに声をかけられ、鳴海はハッとして顔を上げた。
声の主は、カウンターの中にいる白髪の男性――店主の白洲だった。彼は手元の豆を挽く手を休めず、穏やかな視線をこちらに向けている。
「え、あ、はい。……静かで、驚きました。都心にこんな場所があるなんて」
「皆さん、そうおっしゃいます。ここは時間の流れが少し違うので」
白洲はふふ、と柔らかく笑うと、また手元の作業に戻った。
拒絶も歓迎も超えた、ただそこに在ることを許してくれるような空気。鳴海は張り詰めていた肩の力が、もう一段階抜けるのを感じた。
会社に行かなくていいのか。Slackはどうなっているか。
そんな焦りが、コーヒーの湯気と一緒に空気に溶けていく。
カラン、コロン。
その静寂を破ったのは、少し重ためのドアの開閉音だった。
入ってきたのは、上質なリネンのシャツに、使い込まれた革の鞄を提げた男だった。派手さはないが、一目で分かる品の良さと、周囲の空気を冷やすような鋭い気配を纏っている。
「白洲さん。いつもの席、空いてますか」
男は低い声で言いながら店内を見渡し、そして、鳴海の顔を見て止まった。
「……鳴海か?」
鳴海の心臓が、ドクリと大きく鳴った。
見間違えるはずがない。
朝霧 透(あさぎり とおる)。かつて鳴海が所属していた外資系戦略コンサルの元パートナーだ。東大経済学部卒で、30代にして業界屈指の高報酬を得ていた伝説的なコンサルタント。
「構造の悪魔」と呼ばれ、あらゆる事象を論理で解き明かすその思考法に、若き日の鳴海は強烈に憧れ、そして畏怖していた。
「ご無沙汰しております、朝霧さん。……まさか、こんなところで」
鳴海は反射的に立ち上がったが、朝霧は表情を変えずに片手を軽く挙げ、制した。
「座れよ。今は11時だ。丸の内の時計に合わせて動く必要はない」
相変わらずの、感情の読めない声。
朝霧は迷うことなく鳴海の向かいの席に座り、鞄から分厚い洋書を取り出した。
「お前が平日昼間にこんな場所にいるとはな。……どうした、顔色が悪いぞ」
逃げ場は、完全に塞がれた。
◇
なぜ成果を出しても評価されないのか?見落とされた「変数」
「で、評価構造に納得がいっていない、と」
朝霧は、運ばれてきた深煎りのコーヒーを一口飲むと、静かに言った。
鳴海が言葉を濁しながらも、現状の閉塞感――責任だけが増え、権限もポストも与えられない日系大手の実情――を漏らした直後だった。
「納得がいっていないというか……違和感です。成果は出しています。昨日の面談でも、数字は達成しました。でも、『次は期待している』と言葉を濁されるだけです。このまま、いつまで待てばいいのか」
鳴海の言葉を、朝霧は無表情で聞いていた。そして、洋書に挟んでいた栞を抜き取り、テーブルの上で弄びながら口を開いた。
「鳴海。君は優秀なプレイヤーだった。ロジックも組めるし、実行力もある。だが、君は根本的な『変数』を見落としている」
「変数、ですか」
「君の会社、社員は何人だ?」
「……単体で約5,000人ですが」
部長への昇進確率は0.5%未満。大企業の「残酷な算数」
「その母集団の中で、君が目指している『部長』や『本部長』、つまり年収2,000万を超えるポジション(椅子)の数は?」
鳴海は言葉に詰まった。組織図の箱の数は知っているが、それを「数」として、あるいは「確率」として意識したことはなかった。
朝霧は胸ポケットから細いペンを取り出すと、紙ナプキンに無駄のない線で三角形を描いた。
「いいか。日本の伝統的な大企業構造において、年収1,500万を超える管理職の椅子は、全社員の上位5%未満だ。さらに2,000万を超える役員・本部長クラスとなると、0.5%から、良くても2%程度しかない」
朝霧のペン先が、三角形の頂点を小さく黒く塗りつぶす。
「君の今の『課長手前』までは、エスカレーターだ。落ち度さえなければ、君みたいな経歴の持ち主は時間関数で誰でも到達できる。そこには『全員分の椅子』が用意されているからな」
淡々とした口調が、逆に事実の冷たさを際立たせる。
「だが、ここから上は違う。構造が『椅子取りゲーム』に切り替わるんだ。しかも、音楽は鳴り止まないし、椅子は増えない。それどころか、組織のフラット化やAIによる代替で、中間層の椅子は年々焼却されている」
鳴海は反論しようと口を開きかけた。「なら、外へ出ればいい」と。しかし、朝霧はそれすらも見透かしたように、ナプキンの余白に別の数字を書き殴った。
転職市場の真実:2万席の椅子に群がる20万人のエリート
「市場を変えれば勝てる、と思っている顔だな。だが、残酷なことに外部市場も構造は同じだ」
「……え?」
「仮に君が転職で年収2,000万以上を狙うとする。対象になるのは、ベンチャーや中堅企業のCXO、外資のマネジメント、あるいはコンサルのプロジェクトリーダー級だ。だが日本国内に、そういったポジションはざっくり見積もって1.5万から2万席くらいしかない」
朝霧はペン先で、その数字をトントンと叩いた。
「対して、その席を奪い合う君のような――35歳から50歳までの『ホワイトカラーエリート』は、日本に10万から20万人はいる」
数字が、冷たい刃物のように鳴海の喉元に突きつけられる。
2万席の椅子に、20万人が殺到する。倍率は10倍。いや、流動性の低さを考えれば、実質的な倍率はもっと高いだろう。
「でも、実力があれば……ポストが空くのを待てば……」
「それが『労働者の発想』だ」
朝霧は冷たく、しかし諭すように言った。
「上のポストが空くのは、誰かが辞めるか、事業が爆発的に拡大して新しい部署ができる時だけだ。君の会社、今期でどれだけ新しい『部長席』が生産された? むしろ統合されて減っているんじゃないか?」
図星だった。
先月の組織改編で、二つの事業部が統合され、行き場を失った元部長が子会社へ出向になったばかりだ。
第1節で感じた、あの面談室での上司の歯切れの悪さ。
第2節で感じた、中野の家での「生活を守らねばならない」という重圧。
それらが全て、この「三角形の図」と「市場の需給ギャップ」の中に吸い込まれていく。
「君が評価されないのは、能力が足りないからじゃない。物理的に『空き』がないからだ」
朝霧は残酷な事実を、数式の証明終了(Q.E.D.)のように告げた。
「満員の映画館の前で、『私はこんなに映画に詳しいのに、なぜ入れないんだ』と叫んでも意味がないだろう? 中に入りたければ、誰かが死ぬのを待つか、自分で映画館を建てるしかない」
鳴海は、喉が渇いて水を一口飲んだ。冷たい水が、胃の中に重く落ちる。
自分が感じていた「胸のざらつき」の正体は、これだったのか。
見えないガラスの天井。その存在に気づかないふりをして、必死にジャンプを繰り返していただけだったのか。
30代後半の分かれ道。「社内政治」か「物語の外側」か
「30代後半は、残酷な分かれ道だ。いわゆる『スキルや成果の背比べ』のフェーズは終わり、ここからは『限られた椅子』を取り合う勝負になる」
朝霧はコーヒーを飲み干すと、ふと遠い目をした。かつて彼自身も、その構造の中で戦い、そして何かを見て降りたのかもしれない。そんな翳(かげ)が一瞬だけ横顔に浮かんだが、すぐにいつもの鉄面皮に戻った。
「悪いことは言わない。その会社で上を目指すなら、社内政治という変数に全振りするか、諦めて『働かないおじさん』として最適化するか、どちらかだ。……ま、君のような真面目な人間には、どちらも耐え難いコストだろうがな」
朝霧は栞を本に戻し、席を立った。
「じゃあな。……あまり、悩みすぎるなよ」
最後の一言だけは、かつての上司としての情がわずかに滲んでいた。
だが、残された事実は変わらない。
テーブルには、紙ナプキンに描かれた黒い三角形と、打ちのめされた鳴海だけが残った。
店内の静寂が戻ってくる。
だが、先ほどまでの心地よい静けさとは違う。
それは、世界の残酷さを突きつけられた後の、凍りつくような沈黙だった。
自分は、どこへ向かえばいいのか。
会社という物語の先には、もう道がない。
かといって、引き返すこともできない。
呆然とナプキンを見つめる鳴海の耳に、コト、とカップを置く音が届いた。
「……災難でしたね」
顔を上げると、カウンターの中から白洲が、少し困ったような、それでいて何かを慈しむような目で、こちらを見ていた。
(→ 第5節|人材価値の冷徹な鏡、起業という名の「荒野」 へつづく)