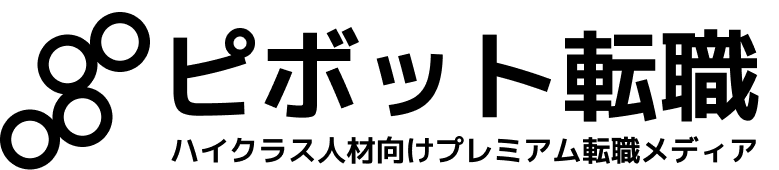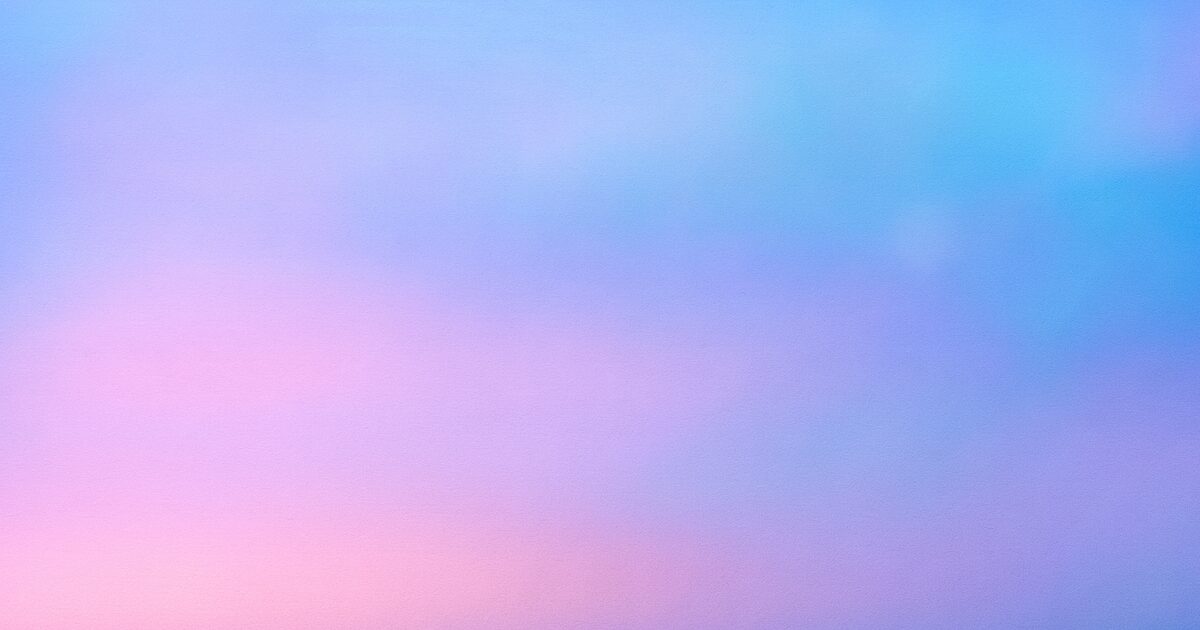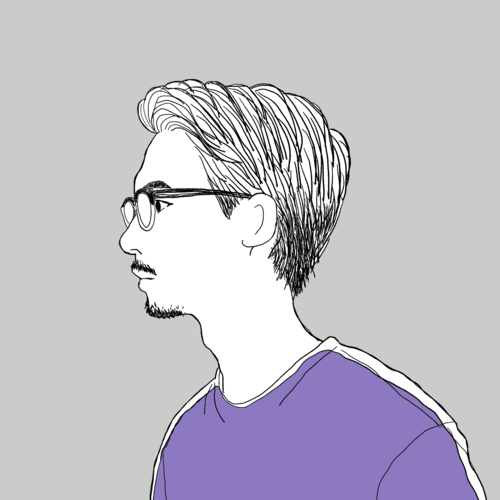「椅子を……買う?」
その言葉の意味を咀嚼するのに、数秒の時間を要した。
私の反応を楽しんだ後、朝霧はグラスに残った氷をカランと鳴らし、静かに解説を始めた。
「そうだ。起業家の才能がないなら、すでに完成されたビジネスモデルを買えばいい。いわゆる『スモールM&A』、あるいは『サーチファンド』と呼ばれる手法だ」
朝霧の話はこうだ。
日本には今、黒字でありながら後継者がいない中小企業が何万社と存在する。彼らは、技術も顧客も、そして毎月確実に振り込まれるキャッシュフローも持っている。足りないのは、それを次代へ繋ぐ「若き経営者」だけだ。
「0から1を生み出すのは、狂気にも似た才能がいる。だが、1を10にする、あるいは10を維持しながら少しずつ磨き上げるのは、君たちのような『エリート実務家』の得意領域だろ?」
朝霧は淡々と言葉を継いだ。
「すでに回っているビジネスを買うということは、時間を買うということだ。プロダクトマーケットフィットに悩み、資金ショートに怯える創業期の3年間をショートカットして、いきなり『社長』の椅子に座る。これが最も合理的で、勝率の高いゲームだ」
目の前の霧が、一気に晴れていくような感覚だった。
そうだ、それなら自分にもできるかもしれない。
今まで培ってきたファイナンスの知識、業務改善のノウハウ。それらを、誰かの承認を得るためではなく、自分がオーナーとして行使できるなら――。
胸の鼓動が早くなる。これこそが、私が求めていた「答え」だ。
「……すごい。それこそ、僕が探していた道です!」
私は身を乗り出した。
「すぐに動きます。今の会社には来週にでも辞表を出して、買収資金の調達とターゲット企業の選定に入ります。退職金も少しは足しになるはずだ」
高揚感に突き動かされ、私は畳み掛けた。
しかし、朝霧の反応は冷ややかだった。
彼は呆れたようにため息をつき、手を振って私の言葉を遮った。
「座れ、早まるな。……これだから『頭でっかち』は困る」
冷水を浴びせられたように、私は動きを止めた。
「何が、駄目なんですか」
「今の君に、誰が会社を売るんだ?」
朝霧は射抜くような目で私を見た。
「君が買収交渉に行く相手は、地元の名士や、叩き上げの創業社長だ。彼らにとって会社は『我が子』そのものだ。どこの馬の骨とも知れない、顔色の悪い都会のインテリ若造に、大事な子供を預けると思うか?」
私は言葉に詰まった。
「君は、彼らと膝を突き合わせて酒を飲み、泥臭い人間関係の中に飛び込めるか? 古参の職人たちにそっぽを向かれず、彼らの生活を背負う覚悟を示せるか?」
朝霧は残酷な事実を突きつけた。
「今の君にあるのは、綺麗なオフィスで作ったパワーポイントと、上司の顔色を伺うスキルだけだ。本物の『人間力』も、生々しい『現場のマネジメント経験』も欠落している。そんな奴が社長になっても、3日で組織は崩壊するぞ」
反論できなかった。
コンサル時代も、今の企画職も、私が相手にしていたのは「数字」と「論理」が通じる相手だけだった。
感情で動く人間、理屈では割り切れない組織の力学。それを御する自信は、正直、ない。
「じゃあ、どうすればいいんですか……」
振り出しに戻った絶望感で、声が震えた。
「今の会社にいても腐るだけだ。かといって、外に出る実力もない。結局、私には何もないじゃないですか」
「だから、『利用しろ』と言っているんだ」
朝霧の声が、低く、強く響いた。
「今の会社を辞めるな。むしろ、今の会社にしがみつけ」
彼は私の目を真っ直ぐに見て言った。
「そして、最短で昇進しろ。今のグレードはL5(係長級)だったな? 死に物狂いでL6(課長級)に上がれ」
「は……? 正気ですか?」
耳を疑った。
あれほどサラリーマンの不自由さを説いていた彼が、なぜ今さら出世を勧めるのか。
「あんな、社内政治と判子リレーだけの世界で昇進して、何の意味があるんですか!」
「意味ならある。そこが、君にとって最高の『無料の道場』になるからだ」
朝霧は指を折って数え始めた。
「L6になれば、部下がつく。年上の扱いにくい部下、やる気のない部下、メンタルの弱い部下。彼らを動かし、チームとして成果を出す経験は、中小企業の社長業そのものだ」
「さらに、課長になればPL(損益計算書)の責任の一端を負わされる。予算を分捕るための社内政治、他部署との利害調整、理不尽な上層部への根回し……。君が今まで『くだらない』と軽蔑していたその泥臭い業務こそが、オーナー社長に必要な『人間力』を鍛えるトレーニングメニューなんだよ」
目から鱗が落ちる思いだった。
社内政治は、くだらない足の引っ張り合いではない。
それは、利害関係者を調整し、自分の目的を通すための「交渉術」の実践訓練だというのか。
「失敗しても、君の腹は痛まない。会社の金で、会社の看板を使って、経営の予行演習ができる。こんなに恵まれた環境はないぞ。ここで成果を出せず、社内の人間すら掌握できない人間に、見知らぬ中小企業のオヤジさんが心を許すはずがない」
朝霧はニヤリと笑った。
「今の会社での出世は、ゴールじゃない。君が『会社を買う』という本当の勝負に出るための、準備運動だと思え」
その瞬間、世界の見え方が変わった。
灰色に見えていた明日からの仕事が、全く別の意味を帯びて迫ってきた。
面倒な上司は「攻略すべき難攻不落の取引先」。
言うことを聞かない部下は「買収先の古参社員」。
理不尽な決裁プロセスは「銀行交渉のシミュレーション」。
そう捉え直した瞬間、身体の奥底から力が湧いてくるのを感じた。
退屈な「労働」が、野心的な「実験」に変わったのだ。
「……分かりました」
私は深く息を吐き、改めて朝霧を見た。
「まずは、L6を取りに行きます。社内の力学をハックして、最短で」
「いい顔になったな」
朝霧は満足そうに頷き、飲み干したグラスを置いた。
「勘違いするなよ。君はもう、会社の『社畜』ではない。会社というリソースを使い倒す『虎視眈々とした捕食者』だ。……さあ、夜が明けるぞ。ゲームの始まりだ」
店を出ると、夜風が心地よかった。
見上げれば、東京の空に白い月が浮かんでいる。
昨晩までは、ただ見上げるだけで溜息をついていた高層ビルの明かりが、今は攻略すべきダンジョンの灯火のように見えた。
私はスマートフォンを取り出し、スケジューラーを開いた。
月曜日の朝一番に入っている定例会議。いつもなら憂鬱で仕方なかったその予定を眺めながら、私は口の端を吊り上げた。
まずは、あの会議室の空気を支配することから始めよう。
新たな道のりは、ここから始まるのだ。
(→ 第2章 第1節|正解という名の落とし穴——戦略的曖昧さ へつづく)