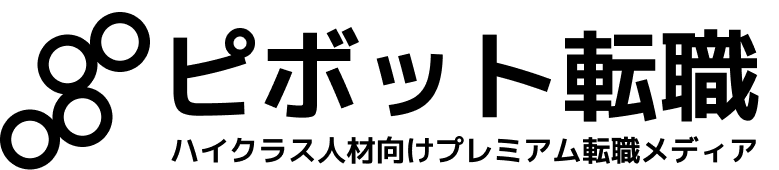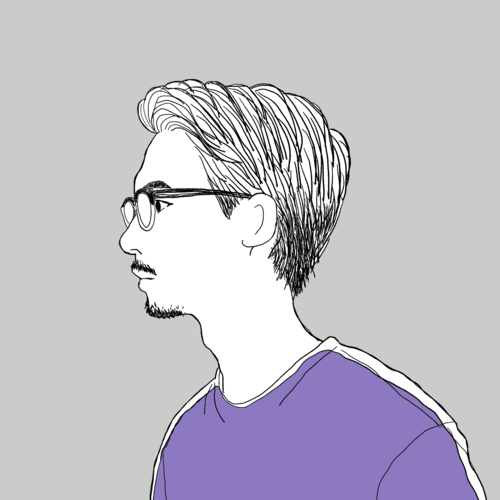1. 完璧な青写真
2030年、冬。東京駅、丸の内側の高層ビル28階。
窓の外には、自動運転のEVバスが整然と列をなして皇居周辺を周回しているのが見える。
鳴海一真(36)は、視界の端に表示されるARグラスの数値を満足げに眺めていた。
「市場成長率予測、4.2%上方修正。競合リスク、低水準にて推移」
専属のビジネスAIアシスタント『ミネルヴァ』が、完璧な声色で囁く。
「よし、これでロジックに隙はない」
数日前、元戦コンの先輩であり、今は独立している朝霧透との会話が脳裏をよぎる。
『鳴海、お前は優秀だ。だが、その優秀さがこの会社で機能していない』
朝霧の言葉は冷徹だったが、核心を突いていた。会社という場所が、合理性だけで回らない「古臭い村」だということは認める。だが、だからといって腐っていても始まらない。
ならば、その「村」の論理さえも凌駕する、圧倒的な「正解」を叩きつけてやればいい。誰にも文句を言わせない成果を出して、このゲームをクリアする。それが、朝霧の言葉を受けて鳴海が選んだ「戦闘モード」だった。
今回のミッションは、社運をかけた新規事業開発プロジェクト「プロジェクト・ネクサス」のリーダー選定コンペだ。
鳴海が用意したのは、物流網のラストワンマイルを、地下の既存インフラと小型ドローンを組み合わせて無人化する構想。
膨大なデータをAIに食わせ、今後10年の収益予測を日次単位でシミュレーションした。「How(どうやるか)」を極限まで詰め切った、完全無欠の計画書だ。
ROI(投資対効果)は明確、リスクヘッジも完璧。誰が見ても「これしかない」という結論に達するはずだ。
「鳴海さん、お時間です。権藤本部長もお待ちです」
声をかけてきたのは、オペレーションチームのリーダーである田島だ。
「りょうかいです」
鳴海は資料転送のジェスチャーをし、自信に満ちた足取りで会議室へと向かった。
2. 統一可能な多様性
会議室には、事業開発本部長の権藤(ごんどう)をはじめ、役員クラスが顔を揃えていた。
先攻の鳴海のプレゼンは完璧だった。
空中に投影されたホログラムグラフが、右肩上がりの未来を約束する。質疑応答も、AIがリアルタイムで生成する回答で、役員たちの懸念を次々と論破した。
「……以上が、我々が取るべき最適解です」
鳴海が締めくくると、室内には静寂が流れた。反論できないのだ。あまりにも正しすぎて。
権藤本部長は「うむ」と唸り、手元のタブレットに目を落とした。だが、その表情はどこか渋い。
次に立ったのは、同期の磯崎だった。
磯崎は、鳴海ほど優秀ではない。ロジックは甘く、いつも「気合い」や「調整」で仕事をしている男だ。彼が持ってきた企画は『地域共創型・未来マルシェ構想』という、タイトルからしてふわっとしたものだった。
磯崎は、データのグラフをほとんど出さなかった。
代わりに映し出したのは、笑顔の老人や子供たちのイメージ映像。そして、彼は役員たちの顔を見渡してこう言った。
「この事業に必要なのは、効率的な配送網ではありません。わが社が100年守り続けてきた『心』を届けることです。このプラットフォームは、まだ何色にも染まっていません。本部長の考える『伝統』、営業担当役員が大事にする『顧客接点』、そして技術担当役員が目指す『革新』……皆様と一緒に、このキャンバスに未来を描きたいのです」
中身がない、と鳴海は思った。
具体的にどうやって収益化するのか? 定義が曖昧すぎる。こんな企画、AIなら0.1秒で「実行不能」のエラーを吐く。
しかし、権藤本部長の顔色が、明らかに変わった。
「……ふむ。未来を描く、か。確かに、最近の我々は数字ばかりを追い求めていたかもしれん」
営業担当の役員も身を乗り出した。
「『顧客接点』か。うん、その観点なら、ウチの部隊も協力できる余地があるな」
技術担当の役員さえもが頷く。
「『革新』のための実験場としても使えそうだ」
嫌な予感がした。背筋に冷たいものが走る。
磯崎のあの中身のない企画が、まるで鏡のように、役員たちそれぞれの「見たい夢」を映し出している。
3. ロジックの敗北
結果は、残酷なほどあっけなかった。
「プロジェクト・ネクサス」のリーダーには、磯崎が選ばれた。
会議室を出た廊下で、鳴海は権藤を呼び止めた。
「本部長、納得がいきません。私の案の方が、収益性は30%も高かったはずです。定義も明確で、実行プランも完璧だった。なぜ、磯崎のあんな……解釈次第でどうとでも取れる案が選ばれるんですか」
権藤は立ち止まり、哀れむような目で鳴海を見た。
「鳴海。お前の企画は、確かに完璧だったよ。100点満点だ」
「なら、なぜ」
「お前の企画には、俺たちが口を出す隙間がなかったんだよ。定義が明確すぎるということは、それ以外の可能性を『排除』するということだ」
権藤はそれだけ言うと、太い背中を向けて去っていった。
口を出す隙間がない? 定義が明確だと排除する?
完璧な正解を作ることが仕事ではないのか?
「ドンマイ、鳴海ちゃん」
磯崎が、悪びれもせず肩を叩いて通り過ぎていく。
「やっぱこれからの時代、AIにはできない『人間力』ってやつ? そこが大事だよねえ」
怒りで視界が歪んだ。
人間力? あのスカスカの企画書のどこに人間力があるというのだ。あれはただの「思考停止」じゃないか。
4. 正しさの向こう側へ
その夜、鳴海は中野の自宅に帰る気になれなかった。
電車は自動的に、神楽坂方面へと彼を運んでいた。
石畳の路地裏、真鍮のプレートに刻まれた『YOHaku』の文字。
重い鉄扉を開けると、カランコロンと乾いた鐘の音が鳴った。
「いらっしゃい」
カウンターの奥で、白洲慧が眼鏡の位置を直しながら顔を上げた。
彼は鳴海の顔を見るなり、ふっと優しく目を細めた。
「……ひどい顔だね。また、『正解』に裏切られた顔をしている」
鳴海は何も言わず、カウンターの端の席にドサリと座り込んだ。
「白洲さん……俺は、完璧でした。AIも、データも、ロジックも、すべてを味方につけたんです。なのに、中身のない『曖昧な企画』に負けました。会社という組織は、結局バカなんですか?」
「……僕がまだ雑誌の編集者をしていた頃、多くの『成功した』ビジネスパーソンを取材する機会があったんだ」
白洲は懐かしむように遠くを見た。
「日本企業という特殊な土壌で、大きなプロジェクトを成し遂げる人たち……彼らには、ある意外な共通点があった」
「共通点……ですか? 圧倒的なリーダーシップとか?」
「いや、逆だ。彼らは皆、『隙』を作るのが天才的に上手かったんだよ」
白洲はコポコポと音を立てて珈琲を淹れながら、静かに続けた。
「鳴海さん。君は企画書という『設計図』を書いた。それは確かに立派な建物だったろうね」
白洲はカップを鳴海の前に置いた。湯気が立ち上る。
「でも、そこに住む『人』の居場所を残したかい?」
「人の居場所……?」
「戦略的曖昧さ(Strategic Ambiguity)。……聞いたことはないかな」
白洲は赤鉛筆をカウンターに置き、真っ直ぐに鳴海を見た。
その瞳は、組織の理不尽さを嘆く鳴海のさらに奥、まだ言葉になっていない問題の本質を射抜いていた。
(→ 第2節|隙間という名の戦略——「共犯者」を作る技術 へつづく)