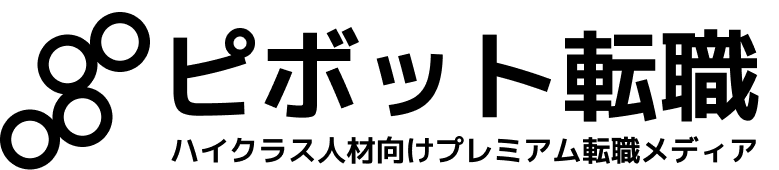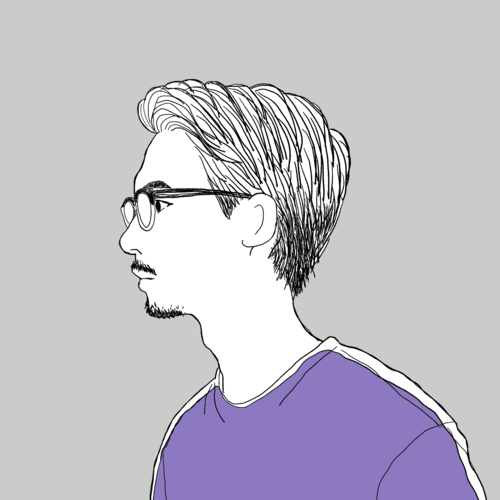神楽坂の路地裏にある『YOHaku』の重い鉄扉を開けると、いつもの静寂とコーヒーの香りが私を迎えてくれた。だが、今の私にはその静けささえも、焦燥感を煽るノイズにしか聞こえなかった。
私はカウンター席に鞄を置くなり、昼間に起きたシステム部との衝突を白洲にぶちまけた。
「……というわけです。谷口部長の態度は明らかにサボタージュでした。『技術的リスク』なんて言葉はただの隠れ蓑だ。本音は、新しい承認フローで自分のハンコが不要になるのが気に入らないだけでしょう」
カウンターの向こうで、白洲は無言でグラスを磨いている。その手元を見つめながら、私はさらに語気を強めた。
「プロジェクトは社長直轄です。谷口部長が首を縦に振らないなら、彼の承認をスキップして、担当役員の決裁だけで進めるつもりです。現場のエンジニアたちは賛成しているんですから、抵抗勢力に付き合っている時間はありません」
そこまで一気に言い切って、私は出された水をあおった。
白洲は磨き終えたグラスを棚に戻すと、ようやくこちらに向き直った。穏やかな表情だが、その目はどこか観察するような光を帯びている。
「鳴海さん。君は企画書という『設計図』を書いた。それは確かに、合理的で立派な建物だったろうね」
不意に核心を突かれ、私はグラスを置く手を止めた。
「ですが、その建物が建つ『地盤』のことを考えたことはありますか?」
「地盤……ですか? どういう意味でしょう」
「以前、数々の企業再建を成功させた、ある『プロ経営者』に取材をした時のことです」
白洲は私の問いには直接答えず、記憶の糸を手繰り寄せるように目を細めた。
「彼の手法は外からはドラスティックに見えましたが、内実は極めて泥臭いものでした。当時、若かった私は彼にこう尋ねたんです。『なぜ、明らかに弊害となっている古参役員を、真っ先に解雇しないのですか』と」
白洲は苦笑しながら、愛用の赤い鉛筆を指先でくるりと回した。
「まさに今の君と同じ疑問をぶつけたわけです。すると彼は、キョトンとしてこう言いました。『彼を追い出したら、彼が抑えていた何百人もの部下の面倒を、全部私が一人で見なきゃいけないだろう? そんなコストの掛かることは御免だね』と」
「……コスト、ですか」
「ええ。君の言う通り、谷口さんは変化を嫌う旧人類かもしれない。だが、彼はこの会社のシステム部という『土地』を20年も治めてきた人間です。部下のエンジニアたちが君に賛成していると言ったね? それは本当かもしれない。だが、もし君が谷口さんの顔を潰して頭越しに命令を下せば、彼らはどう思うでしょう」
「それは……合理的な判断がされたと、思うのでは?」
「いいえ。彼らは『明日は我が身』と恐怖します。自分たちの親分が、外から来た人間に公衆の面前で殴り倒されたわけですからね。その瞬間、システム部は君の敵に回る。表向きは従うふりをしても、現場レベルで微細なサボタージュが始まり、君は彼ら一人一人を監視し、指示を出さなければならなくなる」
私は反論しようと口を開きかけたが、言葉が出てこなかった。脳裏に、谷口の背後にいた若手エンジニアたちの、不安そうな視線がフラッシュバックしたからだ。
「いいですか、鳴海さん。谷口さんに花を持たせ、彼の承認印をもらうこと。それは単なる形式や妥協ではありません。彼のメンツを立てることで、彼に部下を統率させ続けるのです」
「……あえて、彼に仕切らせると?」
「そうです。それが『統治コスト』を下げるということです。君が一人で100人のエンジニアを管理するコストと、谷口さん一人に頭を下げて彼に100人を管理させるコスト。どちらが安いかは明白でしょう?」
白洲は私の前に、注文していない温かいコーヒーをそっと置いた。
「『顔を立てる』というのは、日本的な情緒の話じゃない。極めて合理的な『統治のアウトソーシング』なんですよ」
湯気とともに立ち上る香りが、強張っていた私の肩の力を少しだけ緩ませた。
私は「非効率な老害」を排除することこそが正義だと思っていた。だが、白洲はそれを「安価な管理職」として利用しろと言っているのだ。
「……参りました」
私は小さく呟き、コーヒーに口をつけた。
苦味の奥に、わずかな甘みが広がった。