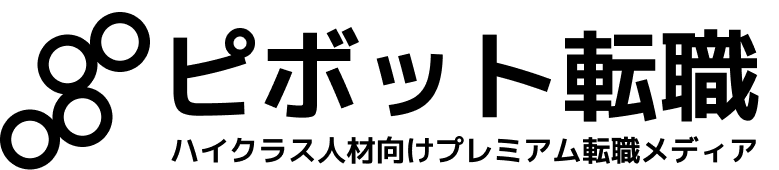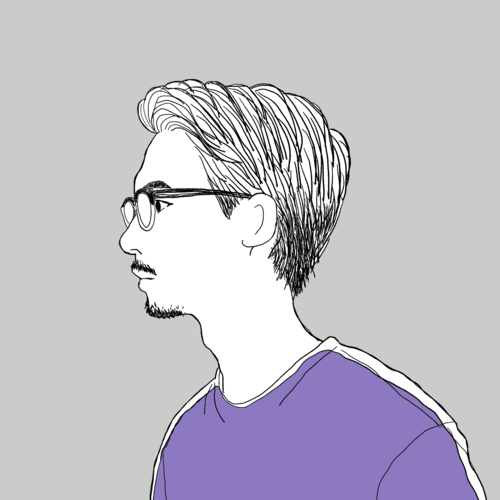東京駅のオフィスビル、28階。 深夜の自動販売機コーナーで、低いモーター音だけが響いている。 僕はそこに、組織図の改訂案を映し出したタブレットを持ち込んでいた。
画面には、営業推進部の組織図。その真ん中にいる「野田 治(52)」という名前に、僕は赤いバツ印をつけていた。
今回のターゲットは彼だ。
1. ボトルネックの排除
野田課長は、社内で「濡れ落ち葉」と呼ばれている。 会議ではニコニコしているだけで発言しない。部下の提案書も、上司の指示も、「まあ、よしなに」と言って右から左へ流すだけ。 AIによる業務分析の結果、彼のPC稼働時間は部内の平均より40%も短かった。
「彼は完全なボトルネックです」
翌日のプロジェクト定例会で、僕は権藤本部長に提言した。 「野田課長を経由することで、意思決定のリードタイムが平均3日遅延しています。彼をプロジェクトから外し、現場のエースと本部長を直結させるべきです」
画面に、新しい情報のパイプラインを表示する。 『中間管理職(ミドル)』という層を抜き、トップの戦略がダイレクトに現場へ伝わる、純度の高い組織図。
「情報の劣化を防ぎ、伝達スピードを倍にする。これこそが、DX時代のフラットな組織です」
権藤本部長は少し考え込んだ後、短く言った。 「……わかった。試してみよう」
野田課長は、プロジェクトのラインから外された。 辞令を受けた時も、彼は「ああ、そうかい。まあ、頑張って」と、相変わらず掴みどころのない笑顔を浮かべていた。 僕は心の中で嘲笑った。危機感すらないのか、と。
2. 直結による「炎症」
しかし、効率化の楽園は訪れなかった。 1週間後に起きたのは、組織の「複雑骨折」だった。
きっかけは、役員会からのトップダウン指示だった。 『来期の生産性を20%向上させるため、全営業ログを新システムに入力せよ』
これまでなら、野田課長が間に入っていた。 だが今は「直結」だ。冷徹な命令が、剥き出しの刃物となって現場のエースたちに突き刺さった。
現場の反応は、即座に爆発した。 「ふざけるな! 今でさえ顧客対応で手一杯なんだ!」 「現場を知らないくせに、数字だけで管理するな!」
そして、その現場の「生の怒り」もまた、フィルターを通さずに経営層へダイレクトに届いてしまった。 「現場のエースだか何だか知らんが、会社の方針に逆らうとは何事だ」 「民度が低い。教育し直せ」
上からの圧力と、下からの反発。 その二つがクッションなしで激突し、摩擦熱で組織が火を吹いた。 現場は萎縮し、あるいは反抗し、プロジェクトの進捗は以前よりも悪化した。
「なぜだ……」 僕は混乱していた。中抜きをして、純度を高めたはずなのに。なぜ毒が回る?
3. トキシック・ハンドラー(毒素処理係)
「鳴海さん。君は組織の『腎臓』を摘出してしまったんだよ」
神楽坂、『YOHaku』。 白洲さんは、僕の話を聞き終えると、静かにそう言った。
「腎臓……ですか? 野田課長は何も生み出していませんでしたが」 「何も生み出さない臓器なんてない。彼はね、**トキシック・ハンドラー(Toxic Handler)**だったんだ」
白洲さんは、コースターの裏に図を描き始めた。 上からの鋭利な矢印と、下からのドロドロした矢印。その真ん中に、丸い円を描く。
「経営層の言葉は『論理(ロジック)』だ。それは正しすぎて、現場にとっては時に鋭い刃物になる。 一方、現場の言葉は『感情(エモーション)』だ。それは熱すぎて、経営層にとってはただのノイズや泥水に聞こえる」
白洲さんは、その真ん中の円を赤鉛筆で塗りつぶした。
「野田さんは、その両方を受け止めていたんだよ。 上からの刃物を、『まあまあ、上も期待してるからさ』とオブラートに包んで現場に渡す。 現場からの泥水を、『彼らもやる気はあるんですが、少し疲れてまして』と濾過(ろか)して上に伝える」
「……つまり、彼は通訳だったと?」 「いいや。**ゴミ箱(Dumping site)**だ」
白洲さんの言葉は冷徹だった。 「組織が動く時に必ず発生する『毒素』や『熱』を、自分の体内に取り込んで処理する場所だ。 彼がいつもニコニコしていたのは、毒を笑顔で中和するためだよ。君はそれを『生産性がない』と断じて取り払った。だから、毒が全身に回って炎症を起こしたんだ」
4. スタビライザーとしての再評価
翌朝、僕はオフィスの喫煙室へ向かった。 そこには、プロジェクトを外れて暇そうにしている野田課長の姿があった。 彼は缶コーヒーを片手に、窓の外をぼんやりと眺めていた。
「……野田さん」 僕が声をかけると、彼は振り返り、いつものように目尻を下げた。 「おや、鳴海ちゃん。どうした、眉間にシワ寄せて」
その笑顔を見た瞬間、僕は理解した。 この人は、ただ笑っているんじゃない。 上からの無茶振りと、部下からの突き上げ。その板挟みのストレスを、この笑顔の裏側ですべて吸収し、無害化していたのだ。 誰からも「仕事をしていない」と後ろ指を指されながら、それでも組織を崩壊させないためのスタビライザー(安定化装置)として、そこに存在していた。
「……いえ。少し、相談がありまして」 僕は頭を下げた。 「現場と本部の調整が、うまくいっていないんです。野田さんの……その、翻訳能力をお借りできませんか」
野田課長は、きょとんとした後、空になった缶コーヒーをゴミ箱に投げ入れた。 カラン、と乾いた音がした。
「翻訳なんて大層なもんじゃないよ。ただの、愚痴聞き係さ」 彼はそう言って笑い、僕の肩をポンと叩いた。 「ま、よしなにやろうか」
その手は温かかった。 僕は自分の完璧な組織図に、再び「野田」という、あえて非効率な結節点を書き加えることになる。 効率という名の病に侵されていた僕が、初めて「不合理な機能」を認めた瞬間だった。