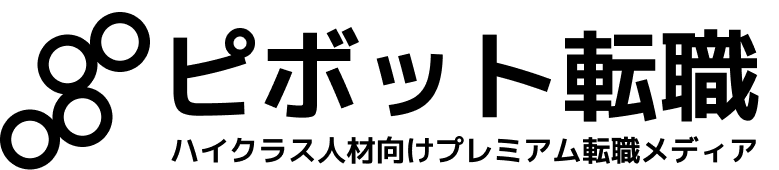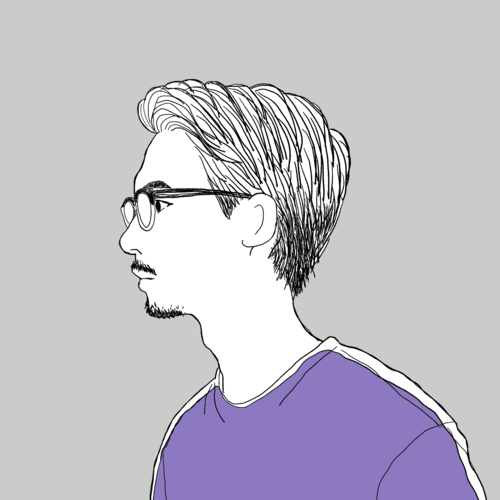プロジェクト・ネクサスの稼働初日。
僕は、モニターに映る「進捗率:0.5%」という数字を睨みつけていた。
すべては効率的に設計したはずだった。
慣例で行われていた関係者500人を集める「キックオフ決起会」や、物流拠点での「安全祈願祭」は、僕の強い提案によりすべて廃止となっていた。
「移動時間とコストの無駄です。目的は『方針の共有』と『安全意識の徹底』ですよね? ならば、動画配信とVRシミュレーションの必修化で十分です」
「えぇ〜、でもさぁ、やっぱり顔合わせないと……」と不満を漏らすオーナーの磯崎や、前例踏襲を主張する総務部を、僕はコスト削減効果の試算表(Excel)で説得し、ねじ伏せたのだ。
情報は100%伝達済み。マニュアルも完備。
なのに、現場は動かない。
チャットツールには、些細な確認事項が嵐のように飛び交っていた。
『本当にこの手順で進めて問題ないでしょうか?』
『万が一のエラー時の責任区分を、再確認させてください』
『念のため、本部の判断を仰ぎたく……』
ドライバーたちの動きが鈍い。彼らは「何をしていいかわからない」のではなく、**「本当にやっていいのか(アクセルを踏んでいいのか)」**を恐れているように見えた。
小さなミスが多発し、そのたびに「聞いていない」「指示が悪い」という疑心暗鬼が広がる。
「情報は完璧に渡したはずだ。なぜ彼らは、こんなに臆病なんだ?」
1. 閉ざされた扉
その夜、たまらず僕は会社を出た。
答えを求めて、足は自然と神楽坂へ向かっていた。
いつもの路地裏。『YOHaku』の重厚な鉄扉の前に立つ。
しかし、扉には小さな木の札が掛かっていた。
『本日、貸切』
「……嘘だろ」
ドアノブに手をかけるが、鍵がかかっている。
中からは微かに、楽しそうな話し声と、グラスが触れ合う音が漏れてくる。
常連客たちの貸切パーティーだろうか。
僕は扉を叩こうとして、手を止めた。
扉一枚隔てた向こう側には、温かい「輪」がある。
しかし、今の僕はその輪に入れてもらえない。
合理性で武装し、他者を排除してきた僕は、ここではただの「部外者」だった。
行き場をなくした僕は、神楽坂の石畳の路地を、あてもなく彷徨った。
2. 異様な熱気
神楽坂の中腹にある、大きな結婚式場としても使われる老舗の会館。
その前を通りかかった時、地響きのような歓声が聞こえて足を止めた。
玄関には**「〇〇建設 大規模再開発 竣工記念祝賀会」**という看板。
開け放たれたロビーには、数百人の人間が溢れかえっていた。
異様な光景だった。
仕立ての良いスーツを着た発注元の役員たちと、作業着や法被(はっぴ)を着た現場の職人たちが、肩を組んで酒を飲んでいる。
顔を真っ赤にして怒鳴り合っている者もいれば、抱き合って泣いている者もいる。
「おい! お前んとこの鳶(とび)が遅れたせいで、納期ギリギリだったんだぞ!」
「うるせえ! 最後に辻褄合わせたのは俺たちだろうが!」
「ガハハハ! まあ飲め飲め!」
カオスだ。
身分も立場も関係なく、数百人が「一つの大きな塊」になってうねっている。
合理性の欠片もない、ただのどんちゃん騒ぎ。
だが、そこには圧倒的な「熱」があった。
その時、人ごみの中から、見覚えのある白髪の男が出てきた。
少し着崩したジャケット姿の、白洲さんだった。
彼は、初老の職人風の男と親しげに握手を交わし、見送っているところだった。
「……白洲さん?」
僕が声をかけると、彼は振り返り、驚いたように目を丸くした。
「おや、鳴海さん。こんなところで」
「白洲さんが、なぜここに?」
「昔担当していた作家先生が、ここの社史を書いた縁でね。断りきれずに引っ張り出されたんだよ」
白洲さんは苦笑しながら、ネクタイを少し緩めた。
僕は会場の喧騒を指差した。
「これだけの人間を集めて、何の意味があるんですか? 酒を飲んで騒ぐだけで、生産性なんてゼロじゃないですか」
3. 雨乞いの論理
白洲さんは、会場の熱気を背に受けて、静かに言った。
「生産性はないね。でも、**『機能』**はある」
「機能?」
「古代、人々は雨が降らない時、雨乞いの踊りをした。
現代の科学で見れば無意味だ。でも、あれには重要な機能があったんだよ」
白洲さんは、会場の中で始まった「手締め」の準備を見つめた。
機能1:不安の鎮静(Anxiety Reduction)
「『これだけ全員で踊ったんだから、神様も雨を降らせてくれるはずだ』。そう思い込むことで、未来への恐怖を麻痺させ、今日を生きる活力を得ていた」
機能2:共犯関係の構築(Complicity)
「そして何より、全員で同じ釜の飯を食い、同じ恥ずかしい踊りを踊る。
それは**『もし雨が降らなくても(失敗しても)、それは踊った全員の責任だ』という空気を作る儀式**なんだ」
会場から、「伊勢音頭」の歌声が響く。
職人も、役員も、全員が声を張り上げている。
「あの現場の職人たちは、明日からまた危険な足場に登る。
彼らを支えているのは、マニュアルじゃない。
『何かあっても、この数百人の仲間がいる』という、非合理な安心感(Ritual)なんだよ」
白洲さんは僕に向き直った。
「君が切り捨てさせたキックオフや祈願祭は、まさにそれだ。
君は情報を伝えたが、『失敗しても、俺たちが守ってやる』という共犯関係を作らなかった。
だから君の部下たちは、たった一人の責任になることを恐れて、アクセルを踏めないんだ」
その時、会場の中心で「よーぉ!」という掛け声が響いた。
パン、パン、パパン。
数百人の手拍子が、完全にシンクロして夜空に響き渡る。
その振動は、僕の身体の芯まで揺さぶった。
4. 非合理な祝祭
翌日、僕は磯崎のデスクへ走った。
「磯崎、緊急で通達を出してくれ。VR研修の補講じゃない」
僕は息を切らせて言った。
「**『プロジェクト・ネクサス 出陣式』**をやるぞ」
「はあ!? お前がやめさせたんだろ? 今さら予算なんて……」
「予算は予備費を全額突っ込む。足りなければ僕のボーナスを削ってもいい。とにかく、ドライバー全員をリアルで集めるんだ。紅白幕も、だるまも、全部用意するぞ」
僕の剣幕に押され、磯崎はポカンとしていたが、すぐにニヤリと笑った。
「……へえ。鳴海ちゃんも、ようやく話がわかるようになったじゃん」
式当日。
会場は500人の熱気で満ちていた。
壇上には、プロジェクトリーダーの磯崎と、実務責任者の僕が並んで立った。
磯崎がマイクを握り、いつもの調子で現場を盛り上げる。
「みんな! 細かいことはこの鳴海ちゃんが完璧に組んでくれた! だから心配すんな!」
ドッと笑いが起きる。
そして磯崎は、僕にマイクを渡した。
僕は深呼吸をし、ロジックを一言も語らなかった。
代わりに、昨夜見たあの男たちのように、腹を割って叫んだ。
「このプロジェクトの全責任は、リーダーの磯崎と、ここにいる我々が負います!
現場で起きるトラブルは、すべて想定内です。
だから、あなたたちは迷わず、アクセルを踏んでください!」
そして、最後に行ったのは、全員での「三本締め」だった。
いい大人が500人、声を揃えて手を叩く。
「よーぉ!」
パパン、パパン、パパンパン。
その瞬間、空気が変わった。
それまでバラバラの粒子だった個人が、熱を帯びた一つの「塊」に変わったのを肌で感じた。
彼らの顔から、迷いが消えていた。
「……そうか。彼らは情報を求めていたんじゃない。**『物語の登場人物になること』**を求めていたんだ」
終了後の懇親会。
僕はビール瓶を持ち、磯崎や現場のドライバーたちの間を回った。
「頼むぞ」「任せてください」。
非効率極まりない「お酌」という儀式を繰り返しながら、僕は組織という生き物の体温を、初めて掌に感じていた。
そのビールは、どんな高級なカクテルよりも、苦くて、旨かった。